
フードコーディネーターの資格は独学でも取得可能です。
ではどんなことをすればいいのか、知りたいところですよね。
そこで今回は食の専門家である「フードコーディネーター」の資格を独学で取得する方法を紹介していきます!
実はフードコーディネーターの資格は誰でも受験資格があって手が届きやすい資格なのです。
資格があると自信にもつながりますよね。
この記事を読むことで、独学でのフードコーディネーターの資格の取得方法がわかります。
あなたもこの記事を参考にして、独学でフードコーディネーターを目指しましょう。
目次
フードコーディネーターの取得は独学でも可能

フードコーディネーターの資格を取得する場合、まずは3級の認定資格を取得することになります。
フードコーディネーターには3級、2級、1級の資格認定試験があるのですが、2級試験には3級の資格が、1級試験には2級の資格が必要になってきます。
まず3級の試験になるわけですが、この合格者は約80%と言われており、その中でも独学で取得している人はたくさんいます。
SNSで探してみると、3級の試験を独学で取得したことを紹介する投稿も多くみられ、比較的取得しやすい資格だと言えます。
3級の資格認定試験は中学卒業以上の人は誰でも受験ができ、資格認定試験は基礎的な問題が多く出題されます。
ですので必ずしも学校に通う必要はなく、教本を購入し徹底的に覚えることで独学で取得可能なのです。
ただ逆を返せば、20%の人は取得できていないのが現実です。
いくら基礎的だからと言っても、食の知識が全くなかったり、勉強不足だったりすれば落ちてしまうのです。
では、どうすれば合格率をあげることができるのか?
独学で勉強していくにもコツがいりますので、そのあたりもしっかりと紹介していきます。
フードコーディネーターの合格率

3級の試験は比較的易しく、合格率は70〜80%程度と考えられています。
実は日本フードコーディネーター協会では3級の合格率が公表されていません。
なぜなら日本フードコーディネーター協会が認定した学校で必要な課程を終了すると、3級の資格を取得できるからです。
試験を受けなくても取得できる3級では、純粋な合格率を出すことができないのです。
ただ、一般的に70〜80%程度と言われています。
2級と1級の公表されている合格率はこちらです。
【2級1次試験合格率】
2023年度 | 85.89% |
2022年度 | 82.39% |
2021年度 | 84.80% |
2019年度 | 86.49% |
2018年度 | 83.85% |
※ 2020年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大により試験・試験対策講座を中止
※ 2018年度より2次試験を2次資格認定講座に変更
出典:2級合格率 | 特定非営利活動法人 日本フードコーディネーター協会
【1級試験合格率】
2023年度 | 29.72% |
2022年度 | 40.00% |
2021年度 | 22.58% |
2019年度 | 43.10% |
2018年度 | 48.57% |
※ 2021年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大により試験対策講座を中止
※ 2020年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大により試験・試験対策講座を中止
出典:1級合格率 | 特定非営利活動法人 日本フードコーディネーター協会
2級、1級試験でも独学での受験が可能ですが、難易度が高くなります。
特に1級試験では合格率が大きく下がっています。
栄養の知識が不足していると感じる人や試験が苦手と感じている人は、専用の講座を受けるのがおすすめです。
フードコーディネーターを独学で取得する勉強法

3級の資格試験がいくら基礎的な問題ばかりで易しいといっても、20%の人が落ちる可能性があります。
再度言いますが、食の知識が全くなかったり、勉強不足だったりすれば試験に落ちてしまうのです。
では実際に合格した人がどのように勉強していたのか。
それをこの記事では紹介していきます。
この通りに勉強すれば、合格する可能性は十分高まります。
ぜひ確認してみてください。
フードコーディネーター3級を独学で取得する勉強法は、教本を購入し、ひたすら読み込むことになります。
ではさらに詳しく解説していきます!
テキストを購入して目を通す
まずはテキストです。
教本はこちらになります。
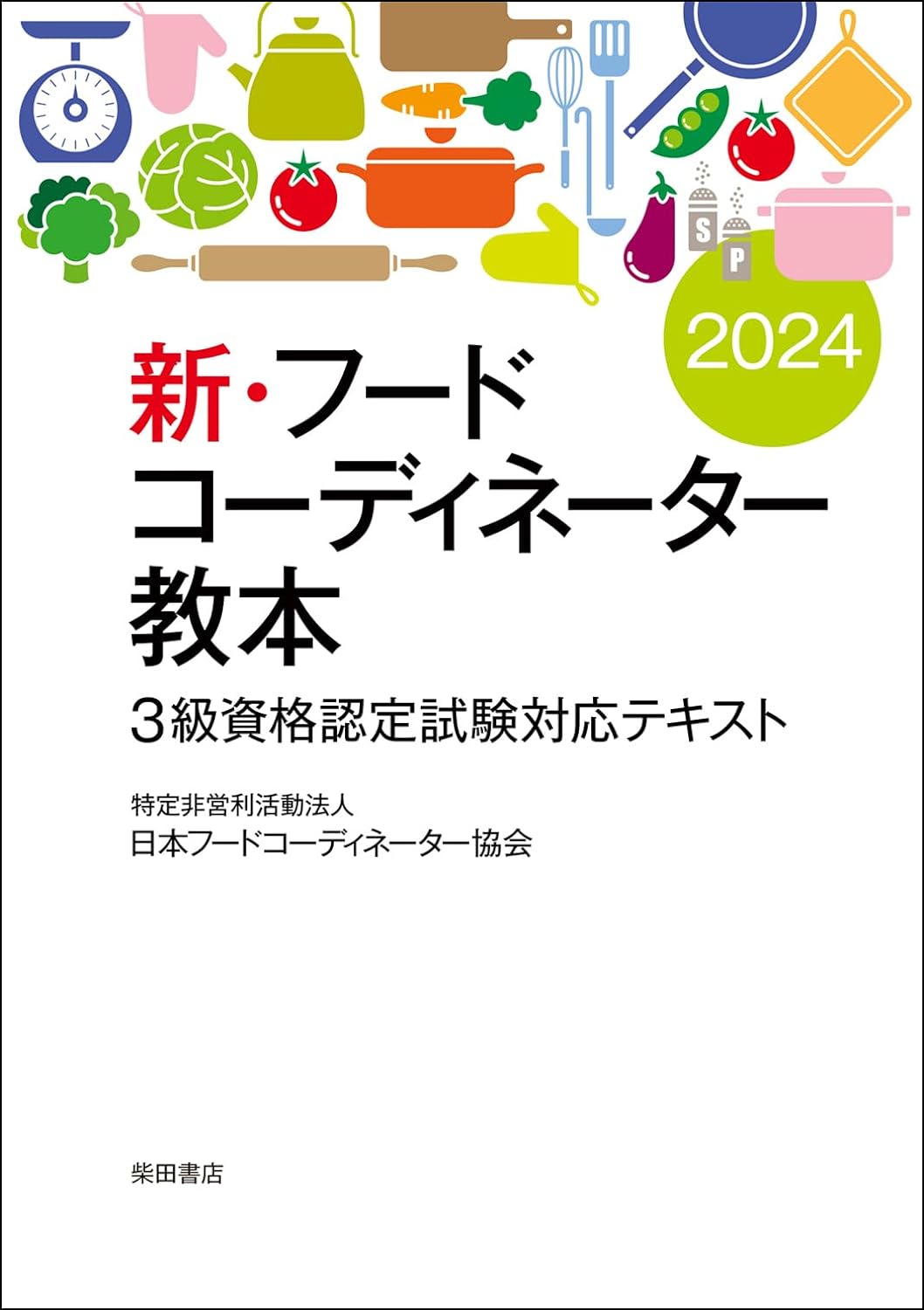
URL:新・フードコーディネーター教本2024: 3級資格認定試験対応テキスト 単行本
購入したらひと通り目を通してみましょう。
テキストには食の文化や調理の基礎知識などが幅広く網羅されています。
テキストは約300ページで、最初から内容を一言一句覚えようとするかもしれませんが、それは失敗のもとになってしまいます。
まずは一通り目を通して、1周目は自分が得意なところや苦手なところを意識して読むといいでしょう。
集中して読めば3時間程度で1周できるでしょう。
そして2週目では、わからない単語や用語を調べながら読み込んでいきます。
3級は食文化や調理の基礎、食の見せ方・ビジネスなど、幅広い範囲ですが一つ一つがそこまで深くはない知識ですので、食に関心があれば十分に合格を目指せます。
用語を関連づけて覚える
できるだけ用語を関連付けて覚えるようにしましょう。
実際基礎的な問題ばかりなのですが、一見混乱しそうな言葉や、食材のカット方法、各国の調理の基本などの用語は似ていて覚えにくいものもあります。
ひっかけ問題として出てくることもあります。
これらの解決策として関連付けて覚えることをおすすめします。
いかにもひっかけ問題というような問題にも強くなります。
関連づけるために、例えばスーパーや市場で食材=旬のものを体感してみましょう。
「この食材は今が旬なんだ」とイメージしながら関連付けるのが、もっとも成功の確率を高めるでしょう。
さらに、食材の産地や調理方法を店員さんに聞いて交流することで、実践的な知識を身につけられます。
同じ食材でも店舗によって産地が違うこともあります。
その点を注目してみたり、食材を見ながらイメージして覚えていくと定着しやすくなります。
テキストを読み進めると出てくる知らない単語は検索して、ノートに書いたりして覚えていきましょう。
分野ごとに重要な部分を自分なりに探して、マーカーやハイライトでわかりやすくします。
重要なポイントを自分の言葉でまとめてノートを作成したり、わからない単語や用語を調べることで、さらに記憶の定着に役立ちます。
過去問題をくり返し解く
問題文はテキストに書いてあることから出題され、傾向は過去問題と類似していると言われています。
一般常識問題もあり、例えば、フードデリバリーサービスの代表的なものを選ばせる問題もあります。
その傾向をつかむためにも過去問題を繰り返し解いておくのはおすすめです。
3級の試験はCBT方式の4択のマークシート方式です。
マークシート方式に慣れておくと本番でも落ち着いて解くことができます。
感覚をつかむためにも、くり返し練習の問題を解いておきましょう。
過去問題集は現在は出版されておらず、過去の問題集は中古品を購入することになります。
運よく購入できた場合は、くり返し解いて身に着けていきましょう。
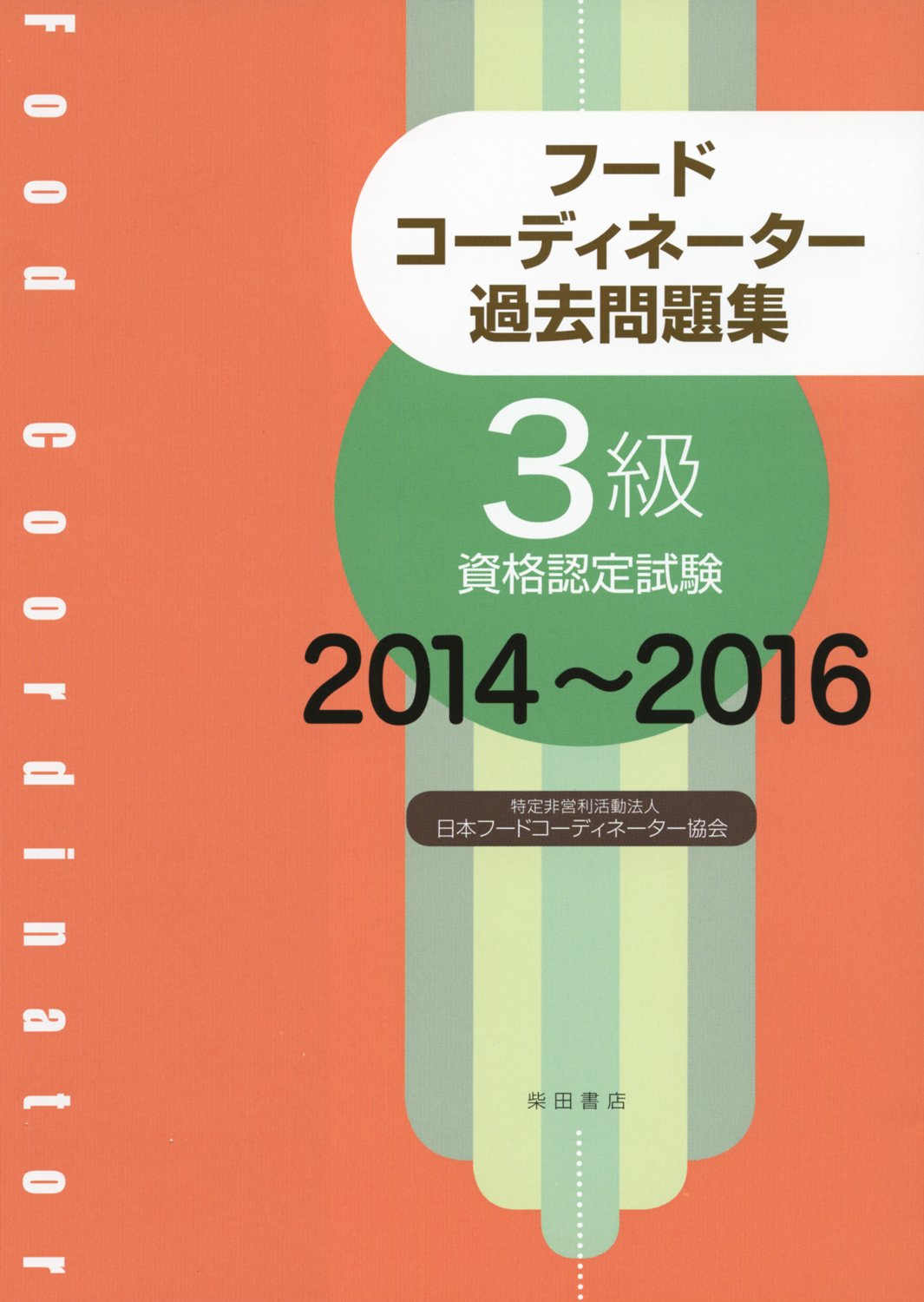
URL:フードコーディネーター過去問題集 2014~2016: 3級資格認定試験 2014~2016
繰り返し解けば解くほど力になり、大切なのは立ち止まらないことです。
さらに詳しい勉強法についてはこちらの記事を確認してください。
フードコーディネーター合格に必要な勉強期間

SNSで確認したところ、独学で合格した人たちの勉強期間は、短くて2~3ヶ月が多く見受けられます。
個人差はもちろんありますが毎日少しずつ勉強するのであれば、この期間で十分合格を目指せます。
ただし元々覚えるのが苦手だったり、食の知識が全くなかったりする人はもう少し延ばすことが必要かもしれません。
早めにテキストを購入し、試験日から逆算してみてどのくらいで覚えられるか目安をつけて、期間を決めて毎日少しづつ勉強していきましょう。
試験内容は食の基本である
- 文化
- 科学
- デザイン・アート
- 経済・経営
の4分野の知識が試されます。
例えば2024年度の試験日程はこのようになります。
試験申込日程 | 2024年8月21日(水)12:00~10月23日(水)23:59 |
試験実施日程 | 2024年11月1日(金)~11月14日(木) |
11月の試験なので、申込日前にはテキストを購入して、確認しておきたいですよね。
まずは一日の勉強時間を確保できるか計画してみましょう。
大切なのは少しの時間でも毎日勉強を続けることです。
フードコーディネーター対策講座を受けた方がいい場合

ここではフードコーディネーターの対策講座を受けた人がいい人の特徴を紹介します。
フードコーディネーター資格認定試験には各級ごとに試験対策講座が開催されています。
各分野の重要なポイントを専門講師がオンラインで講義してくれます。
Web環境さえあれば配信期間中はいつでも何度でも講座を視聴することができる良さがあります。
2級や1級の取得を考えている
2級、1級試験は3級よりさらに実践的な内容になります。
難易度が上がるので、元々食の知識がない場合には独学では難しく、一発合格の確率を上げるために、対策講座の受講をおすすめします。
2級資格ではフードビジネスに関わる専門知識と企画力が試されます。
2級1次試験では、2級テキストに記載の
- レストランプロデュース
- 商品開発
- 食の生産・流通・消費
- ホスピタリティ&ライフサポート
- イベント・メディア
などフードビジネスに関わる専門知識と企画力が試されます。
3級と同じCBT試験で過去問は公開されておらず、どんな問題が出るのかは受けてみないと分かりません。
合格後の2級2次試験では
- 商品開発
- レストランプロデュース
- フードプロモーション
の3分野より一つ選択し、オンライン講座受講後に企画書の課題提出をしなければなりません。
1級資格は、プロとして実践的な知識と技術が試されます。
各分野のスペシャリストとの共同作業の中で、問題と解決法を見出し、的確な方向性を示す能力が求められることになります。
1級1次試験では企画書審査、1級2次試験ではプレゼンテーション・面接があります。
1級試験対策講座では企画書作成の基本を学ぶことになります。
1級試験対策講座は対面形式での講座になります。
定員も決められているので、申込の締切日に注意しましょう。
2級、1級資格認定試験は、内容を聞くだけでも難しく感じるかもしれません。
一回の合格を確実に狙うためには対策講座を活用することがおすすめです。
対策講座の申込は試験の申込とセットになります。
出典:
2級1次試験対策講座 | 特定非営利活動法人 日本フードコーディネーター協会 (fcaj.or.jp)
1級試験対策講座 | 特定非営利活動法人 日本フードコーディネーター協会 (fcaj.or.jp)
集中して勉強できない
独学では「集中して勉強できない」「不安がある」という方にも対策講座がおすすめです。
食の第一線で活躍する現役のプロ講師がわかりやすく説明してくれるため、自然と頭に入ってくるので聴くだけでしっかりと勉強できます。
オンライン講座・オンデマンド配信にて実施され、 配信期間中はパソコン、タブレット、スマートフォン等で視聴可能です。
ちょっとした隙間時間にも視聴できるので、例えば家事の合間だったり、移動中の時間だったり片手間に聞くこともできます。
まとまった時間が取れない人にも良いのではないでしょうか。
どの範囲を集中的に学べばいいか事前にわかるので、試験範囲を効率よく勉強できます。
自分で調べるのが苦手
各分野の重要なポイントを専門講師が解説してくれるので、どこが重要かがわかりやすくより深く理解できます。
独学ではわからない用語は自分で調べなければなりません。
普段からパソコンでの検索に慣れていなくて、一つ調べるのにも時間がかかりすぎてしまう場合は、調べるのが大変で時間もなくなり、嫌になってくるかもしれません。
その点対策講座を受けることで、用語を調べる必要もなく、フードコーディネーターとして必要な基礎知識から、重要なポイントまでを公式テキストに沿って整理することができます。
調べることが苦手な人は、講座を受けて理解するようにしましょう。
試験に合格することはもちろん大切ですが、食に関する様々な用語を自分が理解することが何より大切です。
まとめ
3級のフードコーディネーター認定資格試験は、独学でも取得可能です。
内容も基礎的な問題が多く、普段の食生活に密接しています。
フードコーディネーターへの入口である3級認定資格試験を受けることで、食の世界の広さを感じられ、初心者の方も楽しく学ぶことができる内容です。
合格することで、「食べることが好き」という感覚が「食の分野でこんなことをしたい!」という思いに具体化され、食のプロとしての自信も得られることでしょう。
食への熱意や探求心をお持ちの方は、フードコーディネーター認定資格を取得する第一歩をぜひ踏み出してみてくださいね。



コメント