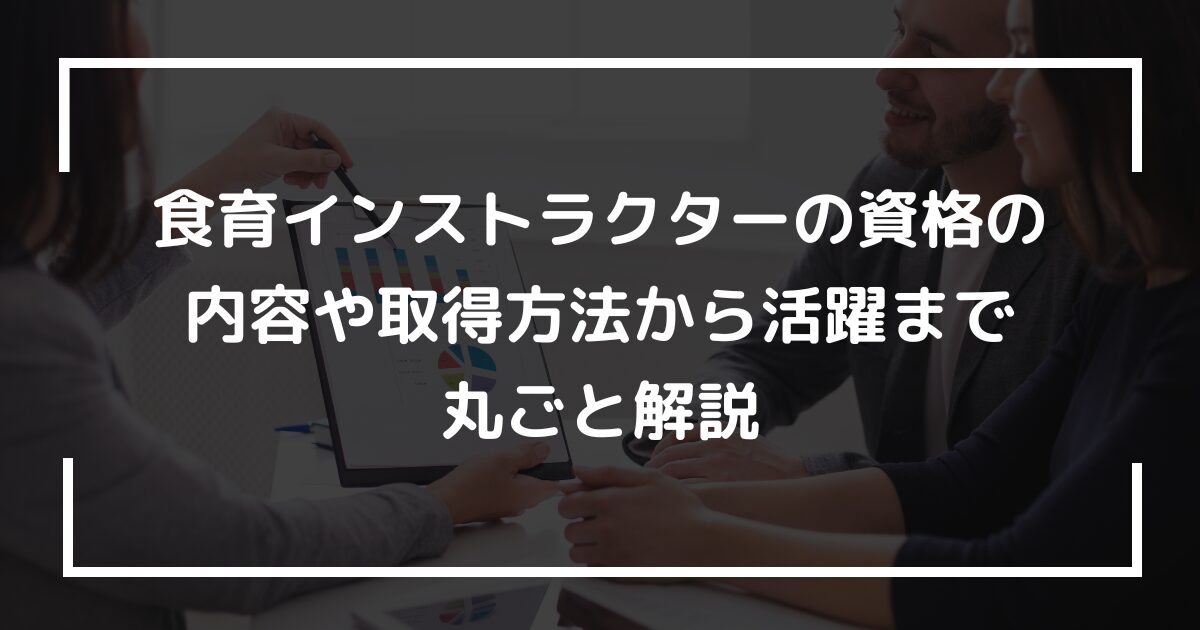
食事や栄養の資格がたくさんある中で、食育に関する資格取得講座もいくつも増えてきました。
それぞれ個性ある内容で、学ぶ側としても多くのことを得られそうですが、実際に選ぶとなるとどれが一番自分に適しているのか分からなくなってきませんか?
一言で「食育」と言っても、実はその内容は非常に幅広く、奥の深いものです。
「食事にまつわる教育ができるようになれたらよい」
「食育と謳ってあればどれでもいい」
と思って選んでしまうと、思ったような内容でなかったり、予定よりも費用や時間がかかったりと、後々後悔することとなります。
せっかくの時間や労力が無駄になってしまうことだけは避けたいですよね。
この記事では、食育インストラクタ―の資格取得講座について詳しくお伝えしていきます。
講座の内容や試験についてはもちろん、取得後に資格を活用していける方法についても解説していきます。
少しでも食育インストラクターに興味のある人は、最後まで目を通していただければと思います。
目次
食育インストラクターの資格について

食育インストラクターという資格は、「特定非営利活動法人(NPO)日本食育インストラクター協会」が主催している民間資格です。
食育を基礎から学んで日々の生活に活かし、広く推進したり、社会で活躍できる食育の指導者であることを証明する資格とされています。
自分に合った方法で実践に役立つ「真の”食育”」を学べる資格、ということです。
取得できる資格は、「食育」の理解や実践のレベル等により、5段階に分けたインストラクター資格として認定されます。
各インストラクター資格は以下の通りです。
- 一級:食育全般に関する幅広い知識と各テーマ(料理・栄養・健康・衛生等)に対する専門知識を持ち、広く伝え、普及活動ができる
- 二級:食育に関する幅広い知識を有し、基本的な知識を分かりやすく伝えることができる
- 三級:食育の重要性を理解し、料理技術を向上させ、日々の生活で食育を実践し身の回りの方々に伝えることができる
- 四級:食育の基本を踏まえ、家庭料理の基礎技術を学び、日々の生活に活かすことができる
- プライマリー:通信教育にて食育の3本柱や基礎知識を学び、問題意識を持ち日々の生活に活かすことができる
この資格取得講座の監修は、主催する協会の理事長も務め、料理研究家としても有名な服部幸應氏によるものです。
通信講座として受講して取得できる資格は、この5段階のうち「プライマリー」のみとなります。
四級以上のインストラクター資格は通学やオンラインなどでの受講となります。
この点については第4章「食育インストラクターの資格取得までの流れ」で詳しく解説していきます。
【出典:特定非営利活動法人 NPO日本食育インストラクター協会】
食育インストラクターの仕事内容

食育インストラクターの活躍する場としては、主に
- 家庭
- 教育現場
- 医療・福祉施設
- 食品業界
等があります。
食育インストラクターの資格取得には、級が上がるごとに、食事や栄養以外に食文化や食を取り巻く状況などについても深く学んでいくこととなり、難易度が上がっていきます。
その学ぶ内容によって、活躍できるフィールドが増えていきます。
ここでは、各フィールドでの仕事内容を紹介していきます。
1.家庭
通信講座で取得できるプライマリーや次の四級では、食の3本柱や基礎的な知識などを学びます。
栄養バランスや食事の指針、食の安心・安全(食材選び、賞味期限・消費期限等)などは、学んですぐに家庭で活かしていくことができる内容です。
日々の食事の支度を考えてみましょう。
献立を考える際、栄養バランスを考慮してメニュー決めを行うことから早速知識を活かしていけます。
次に、食材を購入する際にどのようなものを選ぶことで安心・安全が手に入れられるか、その知識が買い物に活きます。
子供の成長に合わせた献立や、安心して家族で食べられる食材を購入する買い物など、家庭での活用の場は数えきれないくらいありそうですね。
また、家庭から少し飛躍していますが、専門的なところでは、食を楽しみながら学ぶ親子料理教室や、妊産婦・乳幼児を対象とした栄養指導などを仕事としている場合もあります。
【出典:がくぶん】
2.教育現場
近年、教育課程では、自分の住む地域の近隣で取れる農作物や海産物、日本の伝統について学ぶ時間がより多く設けられるようになってきています。
そのため、充実した教育プログラムを作成するために食育インストラクターの資格を取得する人もいます。
特に幼児期の教育として保育園や幼稚園においてはそのような傾向が見られます。
食事の習慣やマナー、食の伝承などの食事にまつわる教育や、食を取り巻く問題(自給率、環境問題・人口問題)などは保育園や幼稚園から小・中学校などの教育現場での食の教育として十分に役立ちます。
特に、食事のバランスや朝食の重要性などの学びは、成長著しい幼児や児童にとって、まさに活きた教育として多くの教育現場で取り入れられています。
地域で摂れた野菜や果物、食肉や魚などの食材を学んで給食と結びつけることで、実際の食事という行為と知識を共通させた地産地消の教育も食育の大切な役割です。
「健康なからだを作る」という自分だけのことではなく、「自分の住む地域について考える」という、自分を取り巻く周りの環境についても深く考えていくことへと繋がります。
また、教育に直接携わる立場でなくとも「給食」は非常に大切な食育の原点です。
食育の知識のある管理栄養士や栄養士、調理師が給食作りに携わることで、より栄養価や安心・安全な給食を子供たちに提供することができます。
このように、教育現場での食育インストラクターの仕事は非常に重要となっています。
3.医療・福祉施設
食育インストラクターを取得して医療や福祉施設の現場で働く場合、すでに管理栄養士や栄養士として従事している場合が多いです。
また、調理員として働く立場で、より食育の内容を活かしたいとして資格を取得し、調理場で働きながらその知識やスキルを活かして管理栄養士や栄養士と共に業務に従事することもあります。
一級や二級の段階まで学習を進めると、生活習慣病や各疾患に合わせた食事内容、ダイエットやサプリメントなどについても学ぶことができます。
また、介護職や妊娠中の食事、乳児・幼児の食事、など一生を通じての食事の在り方を学ぶことができます。
栄養指導や入院や入所者の食事管理などにおいて、元々研鑽してきた知識やスキルをさらにプラスアルファとして、これらの知識を加えることで、より精度の高いサービスを提供することができます。
4.食品業界
食育インストラクターのカリキュラムの中には、冷凍食品やレトルト食品、個食や中食、アレルギーなど、食品業界で必要とされるであろう知識に関して学ぶだけでなく、食の安心・安全にかかわる
「食品安全委員会、食品衛生、トレーサビリティシステム、JAS法、HACCAP、食品添加物、遺伝子組み換え食品、環境ホルモン」
などについても学ぶことで、より専門的知識を活かした食の専門家として活躍することが可能です。
食品業界の身近なところでいうと、スーパーでの料理の実演などがイメージしやすいと思います。
日替わりメニューやオリジナルメニューを実演調理で提案するクッキングサポーター業務などは、調理や食材に関する質問や会話のやり取りをしているように見えます。
しかし、実際にはそれだけではなく、
「健康診断でこんな結果が出たが、食事はどうしたらよい?」
「子どもの好き嫌いはどうしたら直る?」
など、様々なアドバイスを求められることも少なくありません。
そんな時に食育インストラクターでの知識を活かして答えることでスムーズなコミュニケーションをとることができますし、仕事としても幅が出てきます。
また最近では、農林水産物の生産や加工食品の製造を消費者が体験できる企画を食品メーカーなどが行ったり、直売所で直接生産者と消費者とが交流できる機会が設けられたりすることが増えてきています。
都市と農山漁村との交流を進め、生産者と消費者との信頼関係を築くための活動などに、実は食育インストラクターも関わっているのです。
このように、食育インストラクターは様々な分野で活躍することが可能です。
そこには現在の日本で山積みとなっている
「食の安心・安全、健康、家族のだんらんなど、食を取り巻く様々な問題」があり、
食育を実践することで、乱れている現代の「食」の問題を解決していく、という役割が期待されているからでしょう。
【出典】
食育インストラクターの収入

食育インストラクターを取得している人として、
- 和田明日香さん:料理研究家
- ギャル曽根さん:タレント
- 安田美沙子さん:タレント
- 藤本美貴さん:タレント、元モーニング娘メンバー
など芸能界でも活躍している人が多数いることは有名です。
このことから、食育インストラクターを取得することで、就職できたり、仕事が舞い込んでくるイメージがあるかもしれません。
ですが、必ずしも資格取得後から、すぐに活躍できるとは限りません。
むしろ、取得後すぐに大活躍できたり、フリーランスとして仕事を次々にこなす、という人の方が少ない印象です。
食育インストラクターの活躍できるフィールドが様々であることを上でご紹介しました。
活躍できる場が多いということは、それぞれ収入も様々ということになります。
そのため、食育インストラクターの収入は、勤務先や働き方、経験、元々取得している資格などによって異なることがお分かりだと思います。
目安としてお伝えすると、「食育活動」を行っている人の平均的な収入は、年収でだいたい200~300万円といわれています。
では、実際の食育インストラクターの資格を取得した人の例を見ていきましょう。
食育インストラクターの資格を取得して、それを活かして働く場合に多く見られるのが、教育現場や飲食店での調理業務です。
この場合、だいたい月収19~21万円とされています。
しかし、同じ調理業務であっても、大企業などになると月収20~24万円ほどにもなるようです。
一方で、食育インストラクターの資格を取得する場合、元々取得している資格にプラスして取得する場合も少なくありません。
その場合はその勤務先の収入ということになります。
例えば、教育現場において教職員として働きながら教育の一環として食育活動を行う場合の収入は、教員の平均給与である年収約650~750万円となり、食育インストラクター単独で活躍する場合と比較すると、かなり高額となります。
さらに、食育インストラクターの資格を取得してフリーランスで活動する場合があります。
この場合、仕事の内容や依頼数によって収入が変動しますが、中には、年収400万円以上を稼ぐ人もいると言われています。
食育インストラクターの資格は段階を経て級が上がるにつれて、その専門性はかなり高くなります。
その知識や経験を活かして食育インストラクターとしての経験を積み、実績を作ることで高収入を得られる可能性は大いにあります。
【出典】
食育インストラクターの資格取得までの流れ

ここまで、食育インストラクターについて解説してきました。
ここからは食育インストラクターという資格の中身について詳しく見ていきます。
食育インストラクターという資格には5段階の資格があり、それぞれに受講方法や試験が異なっていますので、それぞれインストラクター取得順に詳しく解説していきます。
NPO日本食育インストラクタープライマリー
プライマリー資格は、協会が定める一定の内容の通信教育講座を修了することで取得することができます。
この通信教育講座として指定されているのが、がくぶんの「服部幸應の食育インストラクター養成講座」です。
受講の目安期間として3~6か月が想定され、受講費用は39,900円(事務手数料440円別途必要)です。
学習は全てオンラインで行うこととなり、オプションによるオフラインでの併用学習も可能です。
この養成講座において学べる内容は下記の通りです。
- 1か月目:食生活の基礎知識を身に付ける
- 2か月目:安全な食材の選び方を学ぶ
- 3か月目:食材について詳しく学ぶ
- 4か月目:食事マナーや和食知識、地球にやさしい暮らしを学ぶ
- 5か月目:年代別の食育の実践方法を学ぶ
- 6か月目:食育インストラクターへ
このように5か月目までの課題をクリアすると、そのまま食育インストラクターの資格を取得できる流れとなっています。
NPO日本食育インストラクター四級
四級の資格取得には2通りの方法があります。
1つ目の方法は、推進校への通学です。
この場合、調理実習(6単位)と食育授業(6単位)を受講した後に、食育筆記試験を受験して60点以上で合格となり、4級を取得することとなります。
推進校へ通学する場合の費用は、通学する推進校の規定によります。
2つ目の方法は、協会の主催する研修会に参加することです。
この場合、調理実技の講習を受講した後に調理実技筆記試験を受験し、80点以上獲得することで合格となります。
さらに、資格認定研修会(6単位)を受講し、食育筆記試験を受験します。
この試験は60点以上で合格となり、四級取得となります。
この研修会で四級を取得する場合の受講方法はオンラインで、配信期間は1か月間となっています(令和7年度の場合8月1日~31日)。
試験に関しては、筆記試験とレポートの2科目あります。
筆記試験は、食育と調理に関する内容が講義動画・サブテキスト等から出題され、60点以上合格 が合格となります。
レポートは、調理動画を視聴した後に4品実際に自分で作り、レポートを作成します。
レポートを準備したうえでの筆記試験、という流れとなっており、試験自体はオンライン講義配信の翌日に予定されています(令和7年度の場合9月)。
そのため、資格取得まで有する期間はおよそ3か月間を目安としておくと良いでしょう。
受講費用は、受講受験料(サブテキスト代込み)と申請料を合わせた26,400円 (消費税込み)となっています。
どちらの方法で取得する場合でも、以下の内容を学ぶことができます。
- 食育の3本柱の理解
- 食育基本法
- 食生活指針と食事バランスガイドの理解と活用(朝食の重要性)
- 現代日本の食生活の実態
- 食の安心・安全(食材選び、賞味期限・消費期限等
【出典:非営利活動法人 NPO日本食育インストラクター協会 「資格」取得方法について】
NPO日本食育インストラクター三級
三級の資格取得には4つの方法があります。
1つ目の方法は、「4級取得者で推進校に通学又は一般社団法人全国料理学校協会「上級」取得者」の場合です。
ここに当てはまる場合は、調理実習受講(20単位)と食育授業受講(6単位)又は三級資格認定研修会受講(6単位)を終えた後、食育筆記試験を受験して60点以上で合格となります。
ただし、上級取得者は、調理実習20単位は免除されます。
費用は、推進校の規定によりますが、上級取得者で調理実習が免除される場合は、三級資格認定研修会受講と食育筆記試験受験で合計15,500円となります。
2つ目の方法は、「プライマリー取得者で推進校に通学」する場合です。
この場合は20単位の調理実習を受講することとなり、その費用は推進校の規定によります。
3つ目の方法としては「プライマリー取得者で推進校に未通学」の場合です。
この場合、調理実技筆記試験を受験し、80点以上で合格となります。
試験の受験のみの為、かかる費用はこの調理実技筆記試験代5,500円のみです。
そして4つ目の方法は「食育に関する国家資格等取得者又は当協会賛助会員」の場合です。
この場合、3級資格認定研修会(6単位)を受講後に食育筆記試験を受験し、60点以上で合格となります。
かかる費用は研修会費10,000円と食育筆記試験受験5,500円で合計15,500円となります。
いずれの方法で取得する場合でも、以下の内容を習得したこととなります。
- 食育の3本柱、食生活指針、食事バランスガイドの活動
- 食材についての基礎知識
- 栄養学の基礎知識(五大栄養素等)
- 食習慣とマナー、伝承
- 食を取り巻く問題(自給率。環境問題・人口問題)
- 国・地方公共団体等の取組み
【出典:非営利活動法人 NPO日本食育インストラクター協会 「資格」取得方法について】
NPO日本食育インストラクター二級
二級の資格取得には3通りの方法があります。
1つ目の方法は、「三級取得者で推進校に通学又は食育に関する国家資格等、又は一般社団法人全国料理学校協会「准教師(助教員)」以上取得者」の場合です。
この場合、調理実習(40単位)と二級資格認定研修会(12単位)又は協会認定食育授業(12単位)を受講し、食育筆記試験を受験して70点以上獲得で合格となります。
ただし、食育に関する国家資格等、又は准教師取得者は、調理実習40単位が免除となります。
かかる費用は調理実習費と二級資格認定研修会(12単位)又は協会認定食育授業、受験料ですが、調理実習費は推進校の規定によります。
研修会費や受験料に関しては、他の2つの方法と共通している為、下記の表をご参考ください。
2つ目の方法は、「三級取得者で推進校に未通学」の場合です。
この場合、二級資格認定研修会(12単位)を受講し、食育筆記試験で70点以上、調理実技筆記試験で80点以上獲得することで合格となります。
費用に関しては方法1同様下記の表をご参考ください。
3つ目の方法は、「プライマリー + 食育に関する国家資格取得者」の場合です。
この場合、二級資格認定研修会(12単位)受講後に食育筆記試験を受験し、70点以上獲得することで合格となります。
費用に関しては方法1、2同様下記にの表をご参考ください。
いずれの方法も二級資格認定研修会を受講することになっていますが、この研修会は一・二級合同開催となり、内容は以下の通りです。
- 食の安心・安全2(食品安全委員会、食品衛生、トレーサビリティシステム、JAS法、HACCAP、食品添加物、遺伝子組み換え食品、環境ホルモン)
- 健康増進1(食生活指針、栄養素と栄養バランス、生活習慣病予防(血圧・血糖値・コレステロール値)、骨粗鬆症予防、アレルギー、ダイエット、選食、WHO、特定保健用食品、サプリメント)
- 健康増進2(アレルギー、ダイエット、選食、WHO、特定保健用食品、サプリメント)
- 食の伝承2(旬、郷土料理、行事食、伝統野菜、地産地消)
- 食の形態1(介護食、咀嚼、個食・中食、マタニティー食、乳幼児・成長期の食事、レトルト・チルド・冷凍食品)
- 食の形態2(個食・中食、レトルト・チルド・冷凍食品)
- 食の環境(エコロジー、エコファーマー、世界の食料事情、WHO農業交渉、食料自給率、食の流通)
- 食育活動1(自治体・学校・家庭の取り組み)
- 食育活動2(食育推進活動報告)
- 食育総論まとめ
この研修会の費用についてはこちらの表をご覧ください。
協会会員 | 協会非会員 | |
受講料 | 13,000円 | 25,000円 |
受験料(食育) | 5,500円 | 5,500円 |
受験料(調理) | 5,500円 | 5,500円 |
【出典:非営利活動法人 NPO日本食育インストラクター協会 「資格」取得方法について】
NPO日本食育インストラクター 一級
一級の資格取得には2通りの方法があります。
1つ目の方法として「二級取得者」の場合で、二級取得後1年以上の食育実務経験が必要となります。
この条件をクリアした上で、一級資格認定研修会(12単位)を受講し、食育筆記試験を受験して80点以上で合格となります。
さらに、食育の活動をまとめた「活動報告」と「食育レシピ提案」も資格取得には必要とされています。
食育レシピ提案としては
「エコ料理、地産地消に適する料理、減塩・低カロリー・アレルギー・糖尿病等対策料理などに関し、自らの意見を述べながらレシピを提案をすること、又は、郷土料理・伝統食の歴史やその説明をすること」
とされています。
この場合の費用は下記の表に記していますのでご参考ください。
2つ目の方法は、「栄養教諭」の場合です。
栄養教諭の免許を保持している場合、一級資格認定研修会(12単位)を受講後、食育筆記試験で80点以上を獲得することで合格となります。
二級資格保持者と同様、食育レシピ提案は必要となりますので、上記の内容に関するレシピ提案まで行って、一級の資格取得となります。
一級資格認定研修会の内容は、4-4.NPO日本食育インストラクター二級で紹介した二級資格認定研修会の内容と同様ですので、こちらを参考にしてください。
一級資格取得にかかる費用はこちらの表をご覧ください。
協会会員 | 協会非会員 | |
受講料 | 13,000円 | 25,000円 |
受験料 | 11,000円 | 11,000円 |
【出典:非営利活動法人 NPO日本食育インストラクター協会 「資格」取得方法について】
食育インストラクターに向いている人

ここまでは食育インストラクターという資格について詳しく解説してきました。
活躍できる場などについても紹介しましたが、自分が目指している姿や目標とするところなのか、気になるところだと思います。
ここでは、どのような人が食育インストラクターに向いているのかについて解説していきます。
子どもの成長や家族の食生活が気になる人
食育インストラクターについての学びを真っ先に活かすことができる場は「家庭」です。
特に小さい子供を育てている段階では、やはり子供の成長に必要な栄養やバランスの取れた食事内容という点はとても気になるものです。
我が子が健やかに育つように、との思いをお持ちの人であれば、どなたでもこの資格はおすすめになります。
また、子供に限らず家族全員が健康に毎日を楽しく過ごせるように、との思いで日々食事の支度をしている人であれば、この資格の勉強は必ず役に立ちますし、活用していくことができます。
特に
- 生活習慣病予防をしたいパートナ
- 介護が必要な家族
- 忙しくて外食や中食に頼りがちな離れて暮らす子供や単身赴任の家族
のような人が家族である場合には、この資格を学ぶことで適切な対応ができ、家族の健康を守っていくことに繋がります。
保育所や学校で給食に関わっている・食育をしたい人
食育インストラクターを取得するにあたって
- 一人ひとりが「食」の大切さを見直し、安心・安全・健康な人生を送るために努力する
- 食を通し、心も体も健全に豊かにし育むために食育を学ぶ
ことが、この協会の理念として記されています。
そして
「このことを伝えるために食育を行う」とされています。
プライマリーから1級資格までに学ぶ内容はかなり幅が広く内容も深くなっていきます。
家庭以外でも、小さいころから保育所や幼稚園などで食材に触れたり、簡単な調理実習を行うことは、理念とされる「食を通して心も体も健全に豊かに育む」ことに繋がります。
小・中学校でも調理実習に加え、「旬、郷土料理、行事食、伝統野菜、地産地消」などの知識を食育として学ぶことで、より「一人ひとりが「食」の大切さを見直し、安心・安全・健康な人生を送る」という理念を体感することになります。
このように、教育現場で給食に携わっている人はもちろん、教育者という立場から食育をしたい人には食育インストラクターという資格はおすすめです。
食品業界や健康業界などで仕事に活かしたい人
食に関する資格が溢れるほどある今の状況において、食品業界や健康業界で働く人はどの資格を選んでも活かせるように思えます。
どのくらい食に関する知識やスキルを欲しているかにもよりますが、この食育インストラクターは、先にも述べましたが、級が上がるごとにかなり幅の広い知識を身につけることができます。
それと同時に調理実習や調理に関する試験も受験することとなるため、様々な知識だけでなく、スキルも身につけることができます。
食品業界や健康業界はそれぞれの業界内であっても他業種に分かれるため、求めるものも人により異なります。
その点、受講内容が多岐にわたるこの食育インストラクターは、自分の求める知識やスキルだけでなくプラスアルファで学びを深めることにもなるでしょう。
現在の仕事に活かすことにもなりますし、資格を取得することでさらにステップアップにもつながる可能性もあります。
【出典:特定非営利活動法人 NPO日本食育インストラクター協会】
食育インストラクターと似ている資格

ここまでは食育インストラクターについて詳しく解説してきました。
「食育」について学びたいと思われている人の中には
「他の食育に関する資格も気になる」「この資格との違いは何かを知りたい」
という気持ちがあるかと思います。
ここからは、食育インストラクターと似た名前の資格について3つ紹介していきます。
食育アドバイザー
食育アドバイザーは、一般財団法人 日本能力開発推進協会(JADP)の主催する「JADP認定食育アドバイザー®」という民間資格です。
食育に関する基礎知識を備え、食育活動が行えることを証明する資格であり、「食」に関する知識と健全な食生活を実践するスペシャリストとされています。
活躍の場として、教育、医療、福祉業界はもちろん、飲食業界、食品業界でのプラスアルファの知識としても推奨されています。
資格の取得には、協会指定の認定教育機関として、資格のキャリカレの行う「食育アドバイザー資格取得講座」の全カリキュラムを修了する必要があります。
この通信講座では、
- 食育の基礎知識
- 食品の安全性についての基礎知識
- 食育活動について
- 上記に付帯する基礎知識
について学ぶことができ、全てのカリキュラムを修了すると、そのまま自宅で資格取得試験を受けることができます。
通信講座の受講期間は1日15分の学習で3か月間を目安としており、上記の3項目を1月ごとに学ぶ流れとなっています。
受講料は、3つのコース(サポート期間の違い)によってそれぞれ異なります。
それぞれ
Aコース(サポート期間800日):78,800円 ※Web申し込みで68,800円
Bコース(サポート期間700日):68,800円 ※Web申し込みで19,800円
Cコース(サポート期間600日):58,700円 ※Web申し込みで48,700円
となっており、現在BコースのみWeb申し込みで71%の値下げを行っています(2025年6月現在)。
この受講料に合わせて資格取得試験料5,600円(税込)が必要となります。
資格取得後は、食育についての学びを深め、それを実践したり、人に対して指導することが可能となるため、そのスキルを活かし、セミナー講師や料理教室の講師、教育・医療・食品業界での活躍などが期待されます。
食育インストラクターに関して、当協会のブログでも記載しているものがありますので、興味のある方は、こちらからご確認ください。
【出典】
食育スペシャリスト(現:フード・インストラクター)
食育スペシャリストは、「NPO法人みんなの食育」の「食育スペシャリスト講座」(現在は「食育講座」という講座名)を受講することで認定される民間資格です。
食育を正しく伝えるスペシャリストを目指す通信講座で、入門から中級レベルまで段階的に学びます。
この資格は、「野菜・畜産・穀類・魚・くだもの」の分野で分かれており、全部で5種類の資格が存在することとなっています。
講座自体は、ヒューマンアカデミーの依頼のもと、この法人が監修した職業訓練法人日本技能教育開発センターの「食育講座」を活用し、総合的な食育プログラムとして開発されたもので、講座の運営としては、(訓)日本技能教育開発センターが行っています
そのため、ヒューマンアカデミーですべてのカリキュラムの修了の後にレポートにて修了認定されると、(訓)日本技能教育開発センターから終了証が発行され、NPO法人みんなの食育から認定証が発行される仕組みとなっています。
講座の内容は
- 食べ物を選ぶ力
- 食材の栄養と機能
- 調理法
- 味覚形成
- 食べ物の生育に関する知識
- 流通や品質表示
- 安全表示
など食に関するさまざま知識を身に付けるものです。
資格取得のための試験は設けられておらず、代わりに各講座それぞれ4回の実践課題レポートを提出し、すべての合格をもって資格が認定されます。
講座の受講期間は、それぞれ標準6か月間を目安とされており、在籍期間は12か月間です。
各講座それぞれ受講料は20,900円となっています。
資格取得後は、レシピ開発や商品開発など、食に関する仕事をする人にとっては、食育の考えを取り入れることにより、仕事の幅が広がります。
また、食材の提供者が生活者へ「食育」の観点から食育の価値を説明・提案をすることができるようになることも期待されます。
【出典】
幼児食インストラクター
幼児食インストラクターは、「一般財団法人日本能力開発推進協会(JADP)」が主催している「JADP認定幼児食インストラクター®」という民間資格です。
幼児食の基礎知識から、幼児期の発育・発達と食事の関わり、子どもの成長に合わせた献立の工夫、栄養素の基礎知識、病気・食物アレルギーの対処法など、幅広い知識とスキルを持ち合わせているのが、幼児食インストラクターです。
この資格取得には、協会の認定機関である「資格のキャリカレ」の通信講座である「幼児食インストラクター資格取得講座」を受講する必要があります。
この講座は「週2~3回、毎回15分」という短時間学習で、標準的に3か月間で学びが身に付くとされています。
また、
1か月目:幼児食の基礎知識
2か月目:幼児食前・後期の食事
3か月目:病気の時の食事・食物アレルギー
という内容で学ぶことができ、各内容修了後に添削問題を提出する流れとなっています。
受講料は、3つのコース(サポ-ト期間のみ異なる)によってそれぞれ異なります。
それぞれ
Aコース(サポート期間800日):78,800円 ※Web申し込みで68,800円
Bコース(サポート期間700日):68,800円 ※Web申し込みで19,800円
Cコース(サポート期間600日):58,700円 ※Web申し込みで48,700円
となっており、現在BコースのみWeb申し込みで71%の値下げを行っています(2025年6月現在)。
これらのカリキュラムをすべて終えたら、いつでもそのまま在宅で資格取得試験を受験することができます。
忙しい家事や子育て、仕事の合間に好きな時間で受験することができるのも子育て中の人にはうれしい点でしょう。
資格取得試験の受験料は5,600円です。
合格基準は、得点率の70%以上とされていますが、試験はテキストを見ながら受けられます。
そのため試験や暗記が苦手であっても、安心して試験に臨むことができます。
また、万が一不合格であっても、再試験をいつでも何回でも受けられる、という制度もありますので、その点も安心でしょう。
幼児食インストラクターの資格を取得した後は、
- 幼児食教室の開催
- 自宅料理教室の開催
- セミナー講師業
- 保育園・幼児施設での活用
- 飲食業界・食品業界で活用
など、主に食や料理に関連した分野での活躍が期待されます。
幼児食インストラクター資格取得講座の中にも資格取得後のサポート体制が敷かれており、
専属のキャリアコーディネーターが、求人情報や職務経歴書の書き方、面接のコツの指導などで就職や転職をバックアップするサービスを受けることができます。
また、開業支援サービスとして自分の活動や教室を紹介するホームページを作成する際に、無料テンプレートのプレゼントや、無料での作成サポートも受けることができます。
そのため、資格を取得して、子育ての傍ら個人で起業する、ということも可能です。
【出典】
まとめ
今回は食育インストラクターについて、その資格の内容や取得するまでの流れなどについて詳しく解説してきました。
一口に「食育」と言えども、そのカバーする範囲はかなり幅広く、学びを深めれば深めるほど専門性が上がります。
そのため、活躍できるフィールドも非常に多岐にわたり、自分で切り開いていける可能性もかなり高いものとなります。
人が生きていく上で欠かせない食事の基礎から、衣食住やしつけ、環境などの地球規模での問題に至るまでをひっくるめて学べる資格はなかなかありません。
食にまつわる教育に関心のある人や教育していきたいと思われている人は、是非食育インストラクターに挑戦して活躍していけるよう行動してみてください。



コメント