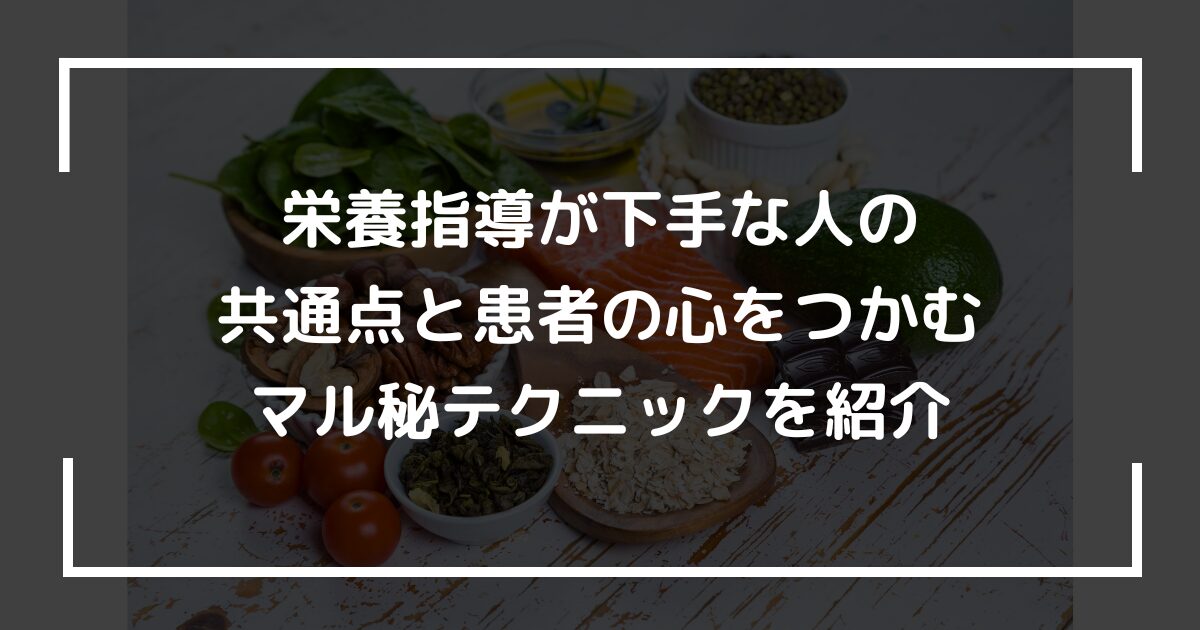
栄養指導が上手くいかないと悩む方は責任感の強い方が多いです。
患者さんに適切なアドバイスをしたいと勉強もしますし、何回もリハーサルをして練習もおこないます。
しかし、コチラから一方的に話す栄養指導になってしまっている…患者さんがアドバイス通りに食事指導を実践してくれない….このような状況に陥ってはいませんか?
でも、大丈夫です。
ちゃんと対処法があります。
あなたのように責任感が強くて、一生懸命にがんばる人のために、患者さんに頼られる栄養指導ができるポイントとテクニックを紹介していきます。
具体的な方法を交えて解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
栄養指導が下手だと感じる人にみられる共通点

栄養指導が下手だと悩んでいらっしゃる方にみられる共通点を知ることで、患者さんからどのように見られているか客観的に自分をイメージできます。
これから3つの共通点を紹介します。
自分も当てはまるからダメだ…と考えるともったいないです。
最初から完璧にできる人の方が少なく、多くの方が悩んでいることでもあります。
自分に当てはまることがあれば改善できるチャンスと思って参考にしてくださいね。
自信がなさそうに見える
自信がなさそうに見えるのも、栄養指導がうまくいかない一つの原因です。
栄養指導の専門家であるあなたが自信がなさそうに見えると不安になってしまいますよね。
自信がなさそうな状態とは、表情・態度・声に現れます。
表情:困った表情をしている、緊張で顔がこわばっている
態度:猫背になっている、リアクションが少なく淡々と話を聞いている
声:早口になってしまう、声が小さい、モゴモゴ喋る、言葉につまる
このような状態だと、患者さんから心配されてしまう可能性が高くなります。
表情・態度・声を意識して、自信があるようにふるまうのがおススメです。
会話のキャッチボールができていない
会話のキャッチボールができていない状態だと、患者さんがアドバイス通り動いてもらえない場合が多いです。
あなたが栄養指導をしている患者さんが「忘れていた」「難しくてできない」と返答した際、次のように答えた経験はないでしょうか?
患者さん「仕事が忙しくて実践できなかったんですよ」
あなた「きちんと続けないと数値も良くならないので頑張りましょうね」
コチラはよくある会話例ですが、実は会話のキャッチボールができていない状態です。
なぜなら、キャッチボールとは相手がボールを受け取りやすいところにボールを投げることだからです。
患者さんは新たな食事習慣を取り入れなければならない状態です。
しかし、返答から察するに、あなたが提案した方法だと患者さんは実践が難しいと感じてしまっています。
このような場合には、患者さんの生活スタイルに応じて取り入れやすそうなスモールステップのアドバイスをしてみてはいかがでしょうか?
例えばこのようなアドバイス例です。
「麺類を食べるときスープは半分以上残すようにできますか?」
「外食するときはご飯を大盛りにしない・おかわりをしないようにできますか?」
「食事量を腹八分と感じる量におさえるようにできますか?」
このようなスモールステップのアドバイス案をいくつか用意しておくとよいでしょう。
そして、患者さんが取り入れやすそうな食事の改善方法から取り入れてもらえるように提案してみてはいかがでしょうか?
患者さんが取り入れやすそうなスモールステップのアドバイスをした上で、患者さんに実践方法を選んでもらうことが大切です。
このような状態だと会話のキャッチボールができているため、患者さんは自分が選んだ方法で食事改善が始められて、あなたの栄養指導で患者さんの数値改善ができる可能性が高くなります。
話す内容が分かりにくい
話す内容が分かりにくい場合も、栄養指導がうまくいかない原因となってしまいます。
あなたは患者さんより疾患についての知識も食事についての知識もあります。
ついつい患者さんに、専門用語を使っていませんか?
患者さんは何となくは理解されているかもしれません。
ただ具体的に説明してと言われると説明できないことも多いものです。
例えば「代謝」を説明する場合、
「代謝とは、車でいえばガソリンと同じような役割をしているんですよ」といったように、例え話を使って伝えるように工夫してみるのも一つの手です。
あなたにとっては当たり前の言葉でも、相手に伝わっていないことがあります。
話の途中途中で内容が確認できているか患者さんに確認してみましょう。
そして、次回から患者さんに伝わる言葉で会話ができるようになると、栄養指導がうまくいっている変化が徐々に感じられるようになっていくでしょう。
事前準備で重要な3つのポイント

ここからは、栄養指導を行う前におこなう事前準備で重要な3つのポイントをお伝えしていきます。
栄養指導では事前準備が「できているか」「できていないか」が非常に重要です。
なぜなら、栄養指導は決められた時間内で一人一人に応じたアドバイスをする必要があるからです。
これから紹介する3つのポイントを押さえて、栄養指導の事前準備の参考にしてみてください。
情報を確認し相手を知る
情報が事前にある場合は、必ず情報(問診票など)に目を通しておきましょう。
年齢・性別・職業・家族構成を中心に確認し、生活スタイルや食事は誰が作っているかなどを予測しておくことで、事前に提案できることを準備しておけます。
情報がない場合は、年齢・性別・職業・家族構成にポイントを絞って尋ねましょう。
栄養指導の時間はあっという間に過ぎてしまいます。
情報を事前に確認して相手を知ることは、次で紹介する「質問事項を決める」に繋がる大事なステップです。
事前情報がないかを必ず確認して、効果的な栄養指導のアドバイスに活かしましょう。
質問事項を決めておく
情報(問診票など)の事前確認ができたら、質問事項のパターンをあらかじめ決めておきます。
栄養指導では疾患別に食事の指導内容が変わりますが、まずは生活スタイルと食事内容の把握が重要です。
■朝食・昼食・夕食を食べるタイミングと食事の傾向は?
■食事は自炊か?買って食べるか?お店で食べるか?
■平日と休日で食事の内容が変わるか?
このように質問事項をあらかじめ決めておくと何を聞けばいいのか迷いません。
併せて質問事項を箇条書きでメモしておくと良いですね。
落ち着いて受け答えができるようになり、栄養指導がスムーズにできるように変化を感じられるでしょう。
さらに、患者さんの返答によって、次で紹介する改善行動のパターンを提案する流れを頭に入れておくように心がけてみてください。
改善行動のパターンを用意する
独身男性、独身女性、既婚男性、既婚女性、年齢とライフステージで大まかな生活スタイルが似通ってくるため、質問パターンを用意しておくのも効果的です。
相手がどのような属性なのか整理しておくことで、改善行動のパターンを用意しましょう。
■独身男性:自炊しないことが多いためコンビニ・総菜や外食の料理の組み合わせを提案
■独身女性:自炊することも外食する場合もある。料理の組み合わせや作り置きなどの料理の提案
■既婚男性:奥さんに料理を作ってもらうことが多いため、奥さんへの食事作りの伝え方。外での食事は独身男性と同じ提案。奥様への食事作りは、既婚女性の食事作りと同じ提案が可能
■既婚女性:家族と一緒に食事を作る際に、食材選定や食べる量の調整および調味料の制限もあるため、自分の分だけ先に取り分けるなどの実用的な提案
今回紹介したのは大まかな提案となります。
最初は色々なことを覚えないといけないため、栄養指導に慣れるまでは「独身」か「既婚」か「自炊する場合」と「外で食べる場合」という大きな属性で捉えることが大切です。
患者さんと接して経験を積む中で属性に応じた提案内容を更新していくと良いですね。
栄養指導が上達するマル秘テクニック3選

事前準備の重要性を伝えてきましたが、ここからは栄養指導の際に指導力があがるマル秘テクニックを紹介していきます。
これから紹介するテクニックを取り入れることで、栄養指導をするたびに患者さんにより伝わるアドバイスができるようになっていきますよ。
相手を理解することに徹する
まずは、相手を理解することに徹しましょう。
なぜなら、あなたがいくら素晴らしい栄養指導をしたとしても、患者ささんの行動に反映されなければ栄養指導がうまくいったと言えないからです。
あなたの役割は、身に付けた栄養の知識を使って、患者様が改善に向かって行動しやすい道のりを先導してあげることです。
そのためにも、相手を理解することはとても重要です。
相手を理解するための栄養指導の方法としては、例えば次のような方法があります。
■患者さんが取り入れやすい行動目標をいくつか提示し相手に選んでもらう
■話の途中で「ここまでの話で分からないことはありましたか?」と確認を取る
このような方法を取り入れることで、患者様に栄養指導の必要性を理解してもらいながら行動に繋げてもらえるようになっていきます。
患者さんが「私のためにこんなに親身になってアドバイスしてくれている」と感じられたら、患者さんの行動も徐々に変わっていくのではないでしょうか。
患者さんを理解し行動してもらうためにも、栄養指導の会話の中から「ヒント」を探すことがポイントです。
結局、相手が実践できそうなアドバイスを提案しないと行動を続けてもらえないですよね。
このように、相手を理解して行動しやすい道のりを整えてあげるイメージで栄養指導をしてみてください。
相手を理解し、相手に応じたアドバイスをすることで、栄養指導に良い変化を感じられるようになっていきますよ。
要点を絞って伝える
短く要点を絞って話すことで相手に話が伝わりやすくなります。
知識があり勉強熱心な方だからこそ起こりやすいのが、アドバイスをしっかりしなければと考えて話が長くなってしまいます。
「相手に正しい情報を伝えたい!」「健康になって欲しい!」という気持ちが強いばかりに、色々とアドバイスをしてしまっていないでしょうか?
多くの方の食事指導をしてきましたが、最初の方は特に、実践できることなんてせいぜい1つか2つです。
ためになるように資料を作り、改善点もたくさん準備して伝えた。
だけど、相手からすれば、最初に食事指導を受ける時が一番重い腰を上げなければならないですよね。
よって、最初こそ要点を絞って話すことが重要です。
患者さんへのヒアリングを通して「大盛りご飯にしないようにできますか?」といった具合に、簡単なスモールステップを用意して伝えるようにしてみてくださいね。
ゆっくりハッキリと話す
栄養指導経験が浅い方に特に意識して欲しいのが、ゆっくりハッキリ話すことです。
患者さんはあなたより年上の方が多いと思います。
あなたのおじいちゃんやおばあちゃんに当たるくらいの年齢の方もいらっしゃるでしょう。
そのため、ゆっくりハッキリ話すだけで患者さんに内容が伝わりやすくなります。
最初は栄養指導に慣れていないため、自信がなかったり責任感を感じて緊張してしまうこともあると思いますが、それは自然なことです。
よって、栄養指導経験が浅い時こそ、ゆっくりハッキリ話すことを意識してみると良いですよ。
例えば、あなたは次のような話し方になっていないでしょうか?
・早口になる
・声が小さくなる
・話が長くなる
これらの対策としては、まず最初は短く話すことを意識しましょう。
そして、話し方が分かりやすいなと思う人をマネしてみると良いですね。
私のおススメは、戦場カメラマンの渡部陽一さんの話し方をイメージして話すことです。
自然にゆっくりハッキリと話ができるようになりますよ。
疾患別のフレームワークを作ろう

栄養指導では、疾患別に注意して欲しい食事の傾向が違ってきますので、疾患別のフレームワークを作っておくと便利です。
例えばこのようなフレームワークです。
糖尿病:血糖値の上昇をゆるやかにする食べ物・食べ方・食べる量
高血圧:高血圧を予防する食べ物・食べ方・食べる量
腎臓病:腎臓に負担をかけない食べ物・食べ方・食べる量
心臓病:心臓に負担をかけない食べ物・食べ方・食べる量
フレームワークを活用して質問やアドバイスをできるようにしていくと、慌てず落ち着いて患者様の声を聞けるようになっていきます。
疾患別に基本は同じアドバイスや質問をします。
そのため、一度フレームワークを作っておけば、プラスで質問することを追加するだけなので作業工程も減り自分の負担も減らすことができますよ。
また、患者様から質問されたことも疾患別にまとめておくことで、次から返答に困らずに適切にアドバイスができるようになっていきます。
フレームワークと質問事項のまとめを活用して栄養指導に活かしてみてくださいね。
栄養指導の数が質を生む

これまで栄養指導が上達する方法を紹介してきてみましたが、最後にお伝えしたいことがあります。
それは、相手に応じたアドバイスができるようになるためには栄養指導の数をこなすことが大切になります。
これまで紹介してきた方法を栄養指導に取り入れると、患者様に適切なアドバイスができるようになっていきます。
しかし、患者様に中々アドバイスが伝わらないと感じる時もあるかもしれません。
そんな時は、今回紹介した方法を繰り返し繰り返し実践していくことで効果的な栄養指導へと繋がっていきます。
今回紹介した方法をチェックリストとして活用しながら栄養指導にいかしてみてくださいね。
まとめ
最後まで読んでみていかがでしたでしょうか?
具体的に実践することが分かり、心が軽くなったのではないでしょうか。
栄養指導に自信がないと感じていたのは、あなたのアドバイスが下手だからではありません。
相手に伝わりやすいポイントを知らなかっただけです。
当協会では、他にも栄養指導の際に役立つ記事を紹介していますので、悩んだときの参考にしてみてください。



コメント