
スポーツトレーナーに必要なことは選手をサポートする総合的なスキルを身につけることです。
実際に指導するにはさまざまな知識が必要になってきます。
そのため、トレーナーとして活躍するためには長い努力と実績の積み重ねが必要です。
競争の激しい業界であることもあり、スポーツトレーナーになる道は狭き門と言えるでしょう。
しかし、諦めずにスキルを磨き続けることで、この門を突破する可能性は広がります。
この記事ではスポーツトレーナーに必要なスキルや特徴、資格、そしてキャリアプランについて詳しく紹介します。
スポーツトレーナーになるためにはどのような知識や経験が求められるのか、またどのようにキャリアを築いていけばよいのか、具体的な情報をしっかりとお伝えします。
スポーツトレーナーを目指す方にとって、役立つ内容が盛りだくさんですので、ぜひ最後までお読みください。
目次
スポーツトレーナーに必要なこととは

冒頭でも記載した通り、スポーツトレーナーには、選手のサポートや現場での適切な対応を行うために幅広いスキルが必要です!
専門的な知識に加え、コミュニケーションや指導力、課題解決、目標設定のスキルが求められます。
そして、これらのスキルを身につけることで、選手やチーム全体の成果向上につなげることができます。
専門知識
これは当然ですが、スポーツに関わる以上、競技に関連する知識を身につけておく必要があります。
しかも、自分の専門分野のこと以外のことも知っておく必要があります。
解剖学、生理学、運動学、トレーニング学、救急対応、リハビリ、テーピング、マッサージ、物理療法、栄養学、睡眠、競技のルールなどです。
例えば栄養学において現場での実践では、試合前後の食事のタイミング管理を基本とし、選手のパフォーマンス向上を目指します。
適切な栄養摂取のタイミングや内容を理解することで、より効果的な競技力の向上が期待できます。
さらに、暑さ対策としての水分補給や遠征時の食事計画など、状況に応じた柔軟な栄養管理が重要となります。
スポーツの現場という、何が起こるかわからない場所で働くためにも、まずは競技に関わる幅広い知識と技術を身につける必要があります。
ただ、これは短期間で身につくものではないですが、現場に出ていくうちに身についていくので、安心してください!
コミュニケーション能力
コミュニケーション能力とは、目の前の選手とだけ話せる能力ではなく、その選手がより良い結果を出すために、その選手に関わっている周囲の人たちと協力することができる能力のことです。
現場では、1人の選手に対して、監督・コーチ、球団フロント、アナリスト、、、多くの人たちが関わっており、それぞれが異なる視点や役割を持っています。
選手に対する支援が効果的であるためには、関係者同士が円滑にコミュニケーションをとることが非常に重要です。
そのために、
- 「他のトレーナーは何を考えているのか?」
- 「コーチは何を知りたいと思っているのか?」
- 「どんな情報をどのような形で伝えるのが良いのか?」
といったように、相手によっても伝える情報・伝え方を変えることも大切なスキルです。
スポーツトレーナーに必要なコミュニケーション能力は、選手との信頼関係を築くことから始まります。
積極的に聞き手になり、選手の気持ちやニーズを理解し、適切な言葉で伝える練習を重ねることが重要です。
また、チームメンバーやコーチとの連携を深めるために、明確で誠実なコミュニケーションを心掛けましょう!
コーチングスキル
トレーナーはコーチングスキルも必要です。
コーチングスキルは選手が少しずつ成果を出し、結果として目標を達成するためには欠かせないスキルです。
コーチングスキルには3つの段階があります。
第1段階:傾聴
選手が悩みを抱えている時には傾聴することで悩みを引き出すことが大切です。
選手が悩みをしっかりと話すためには、相槌などのテクニックで聞いている姿勢を示すことが大切です。
第2段階:質問
選手自身が気づいていないことや悩みの根本的な原因を知るためにも質問を繰り返して選手自身の発見を促します。
第3段階:承認
選手の頑張りを認め、悩みを解決・改善するためのモチベーションアップにつなげます。
このようなコーチングスキルはセミナーや教材で知識を吸収し、それをクライアントとの会話で実践することで身につきます!
問題解決能力
トレーナーが選手に適切なアプローチを提供するためには、選手の理解を深めることが最も重要です。
選手1人ひとりの状態によって、抱えている課題や必要とする能力は違います。
そのため、トレーナーは
- 「この選手におけるベストなアプローチは何か?」
- 「この現場で求められているのはどんな対応か?」
といったことを常に考え、適切に介入することで、課題の解決に努める必要があります。
例えば、怪我の予防や回復を図るためには、選手の身体的状態を詳細に分析し、改善が必要な部分を洗い出して、個別のトレーニングやリハビリプランを立てます。
また、パフォーマンスの向上が求められる場合、選手の技術的な問題点を見つけ出し、具体的な改善策を提案します。
精神的な課題については、選手とのコミュニケーションを重視し、モチベーションを高めるためのメンタルトレーニングやサポートを提供します。
さらに、選手の生活習慣や栄養状態に関する問題を解決するためには、食事や睡眠などの改善策を取り入れ、選手が最適な状態でトレーニングや試合に臨めるようサポートします。
最終的に問題解決能力を駆使して、個別の問題に対して効果的かつ具体的な解決策を提供し、選手が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整えることがスポーツトレーナーの重要な役割です。
課題解決能力を磨くためには、もっとも選手を理解することが大切です。
選手の言葉や動作などからも情報を収集・分析し、選手の課題を正しく理解するように心がけましょう!
目標設定スキル
目標設定スキルとは、目的を必ず達成するための明確な指標を設定できる能力ということになります。
ゴールが決まっていたとしても、その途中のチェックポイントの決め方が曖昧な場合、ゴールにたどり着かなかったり、見当違いな場所にたどり着いてしまいます。
このスキルを身につけるにあたり、まずは明確な目標を立てられるかどうかが前提条件となります。
ただ明確なチェックポイント・目標を立てられるだけでは、この能力を有しているとは言えません。
当然のことながら、自分で立てた目標は達成すべきものです。
とはいえ、トレーナーの立場として、チーム一丸となって達成しなければいけません。
チームの場合は、自分の目標だけでなく、他の人にサポートしたりなど、全員で達成するために管理していく必要があります。
要するに、達成する力とマネジメント力、こちらもおのずと必須となるのです。
スポーツトレーナーに必要な目標設定スキルは、選手のパフォーマンスやリハビリに関する具体的で達成可能な目標を立てることから始まります。
選手と共に目標を設定し、モチベーションを維持するためにフィードバックを積極的に行いましょう!
このようにスポーツトレーナーには、専門的な知識・指導力に加え、選手や関係者と連携しながら課題を解決し目標を達成する総合的なスキルが不可欠です。
これらのスキルを現場で実践し磨くことで、選手サポートの質が高まります。
スポーツトレーナー向いている人の特徴

1章「スポーツトレーナーに必要なこととは」でスポーツトレーナーとして必要なスキルはわかりましたが、実際に活躍するためには、資質や姿勢も求められます!
スポーツへの情熱はもちろん、
- 主体的に学び行動する姿勢
例:最新のトレーニング理論やリハビリ方法を学び、積極的にセミナーや資格取得に取り組む - 地道な努力を継続できる力
例:現場での経験を積むために地元のスポーツチームでボランティア活動を行い、選手一人ひとりの状態に合わせてデータを記録し分析する
これらも必要です。
ここでは、スポーツトレーナーに向いている人の特徴について、具体的に説明していきます。
スポーツが好き
スポーツトレーナーの仕事は、スポーツが好きな人にこそ向いていると言えるでしょう。
スポーツトレーナーを目指す人の中には、その厳しさに圧倒される方も少なくありません。
初めの頃は知識や技術の習得が難しく、体力的にも精神的にも負担が大きいことが特徴です。
また、仕事を続けていく中でモチベーションを保つことが難しく、途中で諦めてしまう人もいます。
しかし、スポーツトレーナーとして成功するために最も重要なのは、スポーツが本当に好きだという情熱です。
スポーツが好きという情熱は、学び続ける原動力になります。
情熱を持ち続けることで、厳しいトレーニングや日々の努力を乗り越え、最終的にはやり遂げることができるでしょう。
スポーツトレーナーの仕事は決して簡単な道ではありませんが、スポーツへの情熱があれば、その先にある大きな喜びと達成感を味わうことができます!
主体的に行動できる
スポーツはルールや戦術など常に進化し続けています。
スポーツトレーナーは、こうしたスポーツの変化に素早く対応しながら新たな知識を主体的に学ぶ姿勢が求められます。
他にも
- スポーツ界の最新動向
- 新しいトレーニング
- ケア方法
- 栄養
- リハビリテーションの最新研究
など、学ぶべき知識はさまざまです。
また、主体的に学ぶ姿勢は選手とのコミュニケーションにも役立ちます。
そのため、スポーツトレーナーは自己啓発の意欲が強く、新しい知識を常に追求し続けられる人が向いています。
継続力がある
しかし、行動力だけでは長期的な成功は難しいかもしれません…。
そこで重要になるのが「継続力」です!
スポーツトレーナーとしてのキャリアは、短期間で成果が現れるものではありません。
長期的な視野で考え、日々の小さな積み重ねが大きな成果を生むことを理解する必要があります。
たとえば、ある治療法の効果がすぐに現れないからといって、諦めてしまうのは非常にもったいないことです。
むしろ、その治療法を継続して試行し、徐々に結果を観察しながら改善を加えていくことで、最適な治療法に近づけることができます。
継続力を持って挑戦し続けることで、選手の満足度を高めるだけでなく、スポーツトレーナーとしての自信とスキルも向上します。
このようにスポーツトレーナーにはスポーツが好きであること、主体的に行動できること、そして継続力がある人が向いていると言えるでしょう!
これらの資質があれば、選手や患者を支えながら自分自身も成長し続けることができます。
スポーツトレーナーとして成功するための大切な要素です。
スポーツトレーナーが取得している資格

スポーツトレーナーになるのに資格は必須ではありませんが、活躍するには資格取得が重要です。
もし、あなたならどちらに頼みたいですか?
- 資格を持たないスポーツトレーナー
- 理学療法士の資格を有しているスポーツトレーナー
当然、理学療法士の資格を有しているスポーツトレーナーの方が信頼感が高いのは明らかです。
スポーツトレーナーが活躍するためには、資格取得が大きな強みになります。
資格は大きく「国家資格」と「民間資格」に分かれ、それぞれ特徴やメリットが異なります。
具体的には以下のような内容があります。
- 国家資格:医療行為が可能で信頼性が高い
- 民間資格:専門性や実践力を高めやすく、取得しやすい
以下ではそれぞれの資格について詳しく説明していきます!
国家資格(理学療法士, 柔道整復師, あん摩マッサージ指圧師, 鍼灸師)
「国家資格」の多くは医療系資格であり、国が定める養成機関で一定期間の修業を行った後、国家試験に合格しないと与えられない資格です。
以下は、国家資格の「理学療法士」「柔道整復師」「あん摩マッサージ指圧師」「鍼灸師」について、それぞれの概要や資格取得に必要な情報を以下にまとめました。
理学療法士
理学療法士はリハビリテーション分野の専門職で、主に身体の運動機能を回復・維持するサポートを行います。
病院やリハビリ施設、訪問リハビリなど幅広い場所で活躍しており、高齢化社会において需要が高まっています。
取得年数 | 専門学校または大学で3~4年 |
費用 | 専門学校:年間100~200万円 大学(国公立):年間50万円 大学(私立):年間100~200万円 |
必要な学歴 | 高卒以上。養成校に進む必要有り |
柔道整復師
柔道整復師は骨折や脱臼、捻挫、打撲といった外傷に対して、非手術的な施術を行う専門職です。
接骨院や整骨院などで働くことが多く、スポーツ現場でのトレーナーとしての活動も注目されています。
取得年数 | 養成校(専門学校または大学)で3年間 |
費用 | 年間150~200万円 |
必要な学歴 | 高卒以上。養成校に進む必要有り |
あん摩マッサージ指圧師
あん摩マッサージ指圧師はあん摩やマッサージ、指圧を用いて疲労回復や痛みの軽減を行う資格です。
整体院や医療機関、訪問マッサージなどで活躍の場があります。
取得年数 | 養成校(専門学校または大学)で3年間 |
費用 | 年間100~150万円 |
必要な学歴 | 高卒以上。養成校に進む必要有り |
鍼灸師(はり師・きゅう師)
鍼灸師は鍼(はり)や灸(きゅう)を使用して、身体の自然治癒力を高める施術を行う専門資格です。
鍼灸院や病院、スポーツ分野など幅広い現場で活躍しています。
取得年数 | 養成校(専門学校または大学)で3年間 |
費用 | 年間100~150万円 |
必要な学歴 | 高卒以上。養成校に進む必要有り |
これらの資格は、医療や健康分野に関わる大切な仕事を担う専門職であり、スポーツやフィットネスの現場でも注目されています。
取得には一定の学習期間や費用が必要ですが、国家資格であるため、医療やスポーツ分野での信頼性が非常に高い点が特徴です。
スポーツトレーナーが取得する国家資格には、以下のようなメリットがあります。
- 社会的信頼性が高い
国家資格は国が認定するため、信頼性や権威が高く、選手やチーム、医療機関からの信用を得やすいです。
- 法的な業務範囲が明確
理学療法士や柔道整復師などの国家資格は、法律で定められた施術や医療行為が可能であり、怪我の治療やリハビリに直接関与できます。
- 活躍の場が広い
医療機関、介護施設、教育機関など、スポーツ現場以外でも活用可能なため、キャリアの選択肢が広がります。
- 安定した収入基盤
民間資格のみの場合と比べて、安定した職業として認識されることが多く、待遇面で有利になる場合があります。
このように国家資格は、社会的信頼性が高く法的に定められた医療行為や施術が可能で、活動範囲が広いのが特徴です。
また、安定した収入や職場環境が得られる場合が多く、キャリアの基盤を築きやすい点がメリットです。
一方で、取得には時間と努力が必要ですが、その分長期的な活用価値が高い資格です。
民間資格(JSPO-AT, JATI-ATI, NSCA)
「民間資格」は、会員登録をするだけの場合もあれば一定の基準を満たす必要がある場合とそれぞれの団体によってばらつきがあります。
以下は、民間資格の「JSPO-AT」「JATI-ATI」「NSCA-CSCS」「NASM-PES」について、それぞれの概要や資格取得に必要な情報を以下にまとめました。
JSPO-AT (日本スポーツ協会認定アスレティックトレーナー)
アスリートのケガ予防やリハビリ、コンディショニングを専門とする資格です。
スポーツチームや現場での活動を中心としています。
取得年数目安 | 1年~2年 ※実技試験有り |
費用 | 30~50万円 内訳:講習会、試験費用等 |
難易度 | やや難(合格率:40~50%) |
必要な学歴 | 高卒以上 ※スポーツ関連の専門学校や大学で学ぶことが推奨 |
出典:アスレティックトレーナー – スポーツ指導者 – JSPO
JATI-ATI (日本トレーニング指導者協会認定トレーニング指導者)
トレーニング指導に関する専門知識とスキルを持つことを証明する資格です。
主にフィットネスジムやスポーツ施設で指導するトレーナー向けです。
取得年数目安 | 3〜6ヶ月 ※独学可 |
費用 | 約10万円 内訳:資格取得費用(試験料や教材費)等 |
難易度 | 中(合格率:約50%) |
必要な学歴 | 制限なし ※運動生理学やトレーニング理論の基礎知識が必要 ※スポーツ関連の学習経験があると有利 |
出典:JATI
NSCA-CSCS (Certified Strength and Conditioning Specialist)
アスリートのパフォーマンス向上を支援するトレーナー向けの国際資格です。
ウェイトトレーニングやプログラム設計に特化しています。
取得年数目安 | 6ヶ月〜1年 |
費用 | 10~15万円 内訳:教材費、試験費用等 |
難易度 | 難(合格率:約50%) ※試験は英語 |
必要な学歴 | 学士号(4年制大学卒業) ※英語の専門用語と運動生理学、解剖学などの知識が必要 ※スポーツ科学や関連分野の学位が推奨 |
出典:NSCAジャパン
NASM-PES (Performance Enhancement Specialist)
NASM(全米スポーツ医学協会)が認定する資格で、アスリートのパフォーマンス向上や障害予防に特化したトレーナー資格です。
取得年数目安 | 6ヶ月〜1年 |
費用 | 10~15万円 内訳:教材費、試験費用等 |
難易度 | やや易(合格率:60~70%) ※試験は英語 |
必要な学歴 | 制限なし ※基礎的な運動科学やプログラム設計の知識が必要 ※運動科学やフィットネス関連の知識があると有利 |
出典:NASM-PES Online資格取得コース | R-body
これらの資格はアスリートのパフォーマンス向上やケガ予防、トレーニング指導に焦点を当てており、スポーツチームやフィットネス施設での活動が主となります。
取得には国家資格ほどの期間は必要ない場合もありますが、基礎的な運動科学や専門知識が求められるため、事前の準備が重要です。
民間資格には、以下のようなメリットがあります。
- 取得のしやすさ
国家資格と比べて、試験や受講の条件が比較的緩やかで、短期間で取得できる資格も多いため、学びやすいのが特徴です。 - 専門性が高い
特定の分野に特化した内容(トレーニング指導、コンディショニング、リハビリなど)が学べる資格が多く、自分の得意分野を伸ばしやすいです。 - 最新の知識や技術を学べる
民間資格は更新や再教育の頻度が高いことが多く、スポーツ科学やトレーニング理論の最新情報を取り入れやすいのが利点です。 - 現場重視の内容
実践的なトレーニング方法や指導技術を学べる資格が多く、すぐに現場で活かせるスキルが習得可能です。 - 資格の種類が豊富で選択肢が広い
自分の目指すキャリアや興味に応じて、必要な資格を選択できる柔軟性があります。
このように民間資格は、専門性を磨いたり実践力を高めたりするのに適しており、キャリアの早期スタートや特定分野でのアピールに役立ちます。
国家資格と民間資格はそれぞれ異なる強みを持ち、スポーツトレーナーとしてのキャリアを支えます。
両者を組み合わせることで、信頼性と専門性を両立させることが可能です。
自分の目指す分野に合わせて、最適な資格取得を目指しましょう!
スポーツトレーナーの仕事内容

スポーツトレーナーの仕事は、トレーナーの種類によって、サポートする内容や目的が異なります。
いずれも選手の健康やパフォーマンス向上を支える重要な役割を担っています。
具体的には以下のような仕事内容があります。
- メディカルトレーナー:ケガのリハビリや復帰支援
- コンディショニングトレーナー:心身の調整やケガの予防
- ストレングストレーナー:筋力向上と身体機能の強化
- アスレティックトレーナー:健康管理やケガの応急処置、リハビリ
次に、これらの仕事内容について具体的に説明していきます。
メディカルトレーナー
メディカルトレーナーは、選手のコンディショニング管理を行ったり、ケガや不調からの復帰をサポートする仕事です。
具体的には、選手がケガをした後のリハビリや、もとのコンディションに戻れるように指導を行います。
コンディショニングトレーナー
コンディショニングトレーナーは、選手がベストパフォーマンスを発揮できるように、心身のコンディション調整や指導、ケガの予防などを行う仕事です。
ケガの予防を目的としたトレーニングメニューの作成といったフィジカル面でのサポートのみでなく、メンタル面からも選手を支援します。
ストレングストレーナー
ストレングストレーナーは、アスリートの身体機能の向上を目指して、主に筋力トレーニングをサポートする仕事です。
状況に応じて、適切に筋肉をコントロールできるように、スピードやバランス、柔軟性、持久力に配慮しながら、トレーニングメニューを作成・指導します。
アスレティックトレーナー
アスレティックトレーナーはスポーツの現場で働き、選手の健康管理やケガの予防の他、ケガをした場合の応急処置やその後のリハビリテーション、体力トレーニング、コンディショニングなどを行い、競技者をさまざまな面から支える仕事です。
これらのトレーナーはそれぞれの専門性を生かし、選手の成長と競技力の向上を支えています。
スポーツの現場で欠かせない存在として、多くの選手にとって大きな力となるでしょう。
自分の強みを生かして、目指す分野に挑戦してみてください!
スポーツトレーナーのキャリアプラン
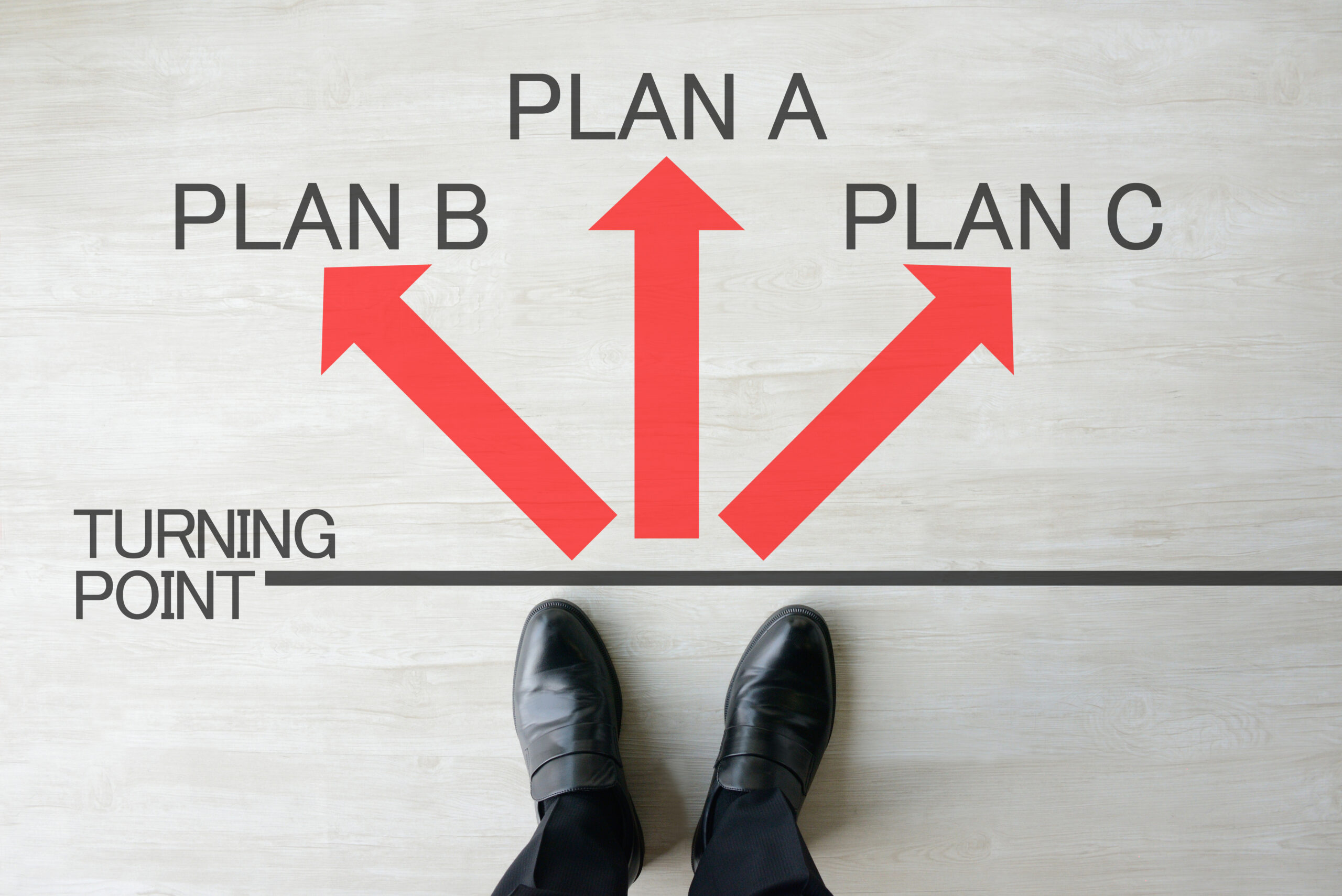
スポーツトレーナーとしてのキャリアプランは以下のように進めると考えます。
- 基礎資格の取得
3-2「民間資格(JSPO-AT,JATI-ATI,NSCA)」で紹介したような資格で、基礎的な知識と技術を学び現場での即戦力を身につける。 - 現場経験を積む
スポーツチームやフィットネスジムで経験を重ね、選手やクライアントとの実践力と信頼を培う。 - 専門性を高める資格を取得
3-1「国家資格(理学療法士, 柔道整復師, あん摩マッサージ指圧師, 鍼灸師)」で紹介した国家資格を取得することを推奨。
さらにステップアップしたい方は、3-2「民間資格(JSPO-AT,JATI-ATI,NSCA)」で紹介した民間資格の上位資格(CSCS、AT資格)(※)を取得することで、リハビリやパフォーマンス向上に関わる幅広いスキルを獲得。
※民間資格の上位資格(CSCS、AT資格):国際的な資格や4年制大学卒業後でないと取得できない資格 - ネットワークと実績の構築
プロスポーツチームや地域コミュニティでの活動を通じて実績を積み、人脈を広げる。 - 指導者や教育者へのステップアップ
経験を活かして若手トレーナーの育成や、専門家としてセミナーや教育活動に取り組むことでキャリアの幅を広げる。
キャリアプランを明確に描き、これらの着実にステップを踏むことで、スポーツトレーナーとしての可能性が広がります。
基礎から専門性、そして教育者への道まで、自分の目指す姿に向かって努力を続けてください!
スポーツトレーナーになるのは狭き門

スポーツトレーナーとして活躍するには、プロスポーツの現場やトップアスリートとの関わりを目指す場合、競争が非常に激しく、狭き門であることは間違いありません。
その中で他のトレーナーと差をつけるためには、トレーニング指導やリハビリスキルに加えて、栄養学の知識を深めることが有効な戦略となります。
スポーツトレーナーにとって、栄養学は非常に重要な要素です。
リハビリやストレングスに集中しがちですが、実際には栄養もパフォーマンス向上に欠かせません。
運動をする際、私たちはエネルギーを消費しますが、そのエネルギー源となるのが糖質などの栄養です。
これらが不足すると、身体が十分に機能せず、パフォーマンスが低下してしまいます。
結果として、スポーツトレーナーとしての信頼性も損なわれる可能性があります。
今後、自分のスキルをさらに磨きたいと思っている方には、栄養学を学ぶことが非常に有益です。
特に、臨床栄養医学協会での学びは、単なる栄養学の基礎を超えた、臨床的な観点からの深い知識を習得できる点が大きな強みです。
これにより、選手のパフォーマンス向上やコンディショニングサポートに必要な栄養計画を立てるスキルを身につけることができます。
加えて、怪我や疲労の回復を促す食事提案など、栄養士顔負けのアプローチが可能となり、チームや選手から信頼を得る大きな武器となります。
トレーナーとして活躍するには、選手の体を総合的に理解し、トレーニング・リハビリ・栄養という複数の視点からサポートできるスキルが求められています。
栄養学を学ぶことで、他のトレーナーとの差別化を図り、現場で「求められる人材」として存在感を高めることができるでしょう。
狭き門を突破するには、栄養の知識を武器にすることが大きな一歩となります。
参考: 臨床栄養医学協会
まとめ

スポーツトレーナーとして活躍するためには、専門的な知識や技術に加え、選手やクライアントの心身の状態を理解し、信頼関係を築くコミュニケーション能力が欠かせません。
現場では状況判断力や問題解決力が求められるため、継続的に最新のトレーニング理論やスポーツ栄養学を学び、実践に取り入れる姿勢が必要です。
特に、ケガの予防やパフォーマンス向上には、トレーニング指導だけでなく、栄養管理のサポートも重要です。
さらに、選手一人ひとりの体質や競技特性に合わせた栄養指導を行い、回復促進やコンディショニングの最適化を図ることで、トレーニング効果を最大化することができます。
正しい栄養指導はスポーツトレーナーとしての信頼も向上するでしょう!
この記事がスポーツトレーナーとしての成長とキャリアの充実につながることを願っています!



コメント