
患者さんに効果的な食事指導をするためには、まず患者さんについてしっかりと情報収集したうえでアセスメントを行い、個別性に合わせた指導内容を考える必要があります。
また、患者さんの思いや訴えに寄り添いながら関わることもとても大切です。
看護師は入院患者さんにとって、一番身近な存在であり、だからこそ看護師にしかできない食事指導の関わり方があります。
ただ、実際に患者さんに食事指導をすることになった時、一体どんな風に伝えればいいのか悩むことはありませんか?
改善点を伝えるだけの指導になってしまっている人も多いのではないでしょうか。
しかし、いきなり「あれはダメです」「これは控えましょう」などと一方的に伝えても、素直に行動に移せる人は少ないですよね。
かえって、看護師の話を素直に聞いてくれなくなる可能性もあります。
この記事では、入院患者さんに食事指導を行うときの、準備から実施に至るまでの具体的な方法をお伝えします。
最後まで読めば、食事指導の一通りの流れが理解でき、患者さんとの関わり方のポイントもおさえることができます。
実習生の人や新人看護師として初めて食事指導をする人は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
食事指導における病棟看護師の役割とは

食事指導における病棟看護師の役割は、「患者さんが行動に移せるように、患者さんの気持ちに寄り添いながらサポートすること」です。
食事指導をするということは、今の患者さんの食事内容や食事方法を変えるということです。
それって患者さんにとっては、すごくストレスになることが予想できますよね。
例えば、毎食欠かさず味噌汁を飲んでいたのに、塩分過剰になるから1日1食にしてくださいと言われたらどうでしょう。
料理が美味しく感じなくなったり、食事の中で楽しみがなくなって、食事自体が嫌になるかもしれません。
食事指導を受けるということは、患者さんにとっては「何を言われるんだろう」「自分の生活がどう変わるんだろう」と身構えてしまうこともあると、指導する側は理解しておく必要があります。
そのうえで、もっと具体的な病棟看護師の役割を以下にまとめました。
- 患者さんや家族から入院前の生活について情報収集する
- 情報や問題点を他職種と共有する
- 患者さんの希望を他職種と共有する
- 患者さんが疑問や不安を感じていないか観察しコミュニケーションを図る
- 退院後の生活についてアセスメントする
これらの役割をしっかり理解して食事指導することで、患者さんの周りの環境を整えることができ、患者さんの気持ちにも寄り添うことができます。
結果的に、患者さんは指導されたことを行動に移しやすくなります。
食事指導は栄養士の仕事というイメージもあると思いますが、看護師と栄養士それぞれに役割があります。
こちらの記事で詳しく解説しているので、よければ確認してみてください。
病棟看護師による食事指導の実際

ここでは、食事指導の現場でやってしまいがちな看護師の対応や、患者さんが抱きやすい不満について紹介します。
心当たりがある人は、ご自身の指導を振り返る機会にしてくださいね。
患者さんに食事指導をすることになったとき、まず何から始めますか?
患者さんの現在の食事の問題点を見つけ出し、それを改善できるようにアドバイスをしよう、と考える人が多いと思います。
しかし、患者さんの多くは、自分の食事に問題があることはなんとなくわかっています。
それでも変えられないから困っているんですよね。
また、手術などで食事形態や食事回数を変える必要がある患者さんでは、今までとは全く違う食習慣を取り入れるわけですから、戸惑ってしまうのも無理はありません。
そんな患者さんに対して、「必要なことだから頑張りましょう!」と言うだけでは、患者さんの気持ちを無視した指導になってしまいます。
例えば、こんな指導をしていませんか?
- 脂っこいものは控えたほうがいいですよ
- 味付けは薄めを意識しましょう
- できるだけ魚も食べるようにしてくださいね
- 野菜は毎食両手いっぱい食べるようにしましょう
このように、理想の食事を伝えるだけでは、患者さんも行動に移す気にはなれませんよね。
逆に、今の自分を否定されたように感じて、看護師に心を閉ざしてしまう可能性もあります。
食事指導をするためには、まず患者さんの生活背景や価値観など、患者さん自身を知ることから始める必要があります。
患者さんが大切にしていることや、生活の楽しみになっていることを知ることで、その方の生活に沿った食事指導ができ、患者さんも聞き入れやすくなります。
基本となる食事指導の手順

実際に食事指導をするとなったとき、いきなり患者さんのもとへ行ってお話する訳ではありません。
これらの5つのステップに沿って行っていきます。
- 情報収集
- アセスメント
- 看護計画の立案
- 看護計画の実施
- 評価・修正(例:SOAP記録)
ここでは、それぞれの手順を詳しく解説していきますので、実際の患者さんにも当てはめて考えてみてくださいね。
情報収集

看護師は業務量も多く、栄養指導の時間も決して多く取れるわけではありません。
ですから、必要な情報を得るために、普段から意図的にコミュニケーションを取っていく必要があります。
情報収集する内容を以下にまとめたので、参考にしてください。
・現病歴、既往歴、アレルギーの有無
・治療方針、治療経過、医師の指示、投与薬剤、
・検査データ(血液検査/画像検査/その他)
・バイタルサイン、身体症状、ADLとリハビリの状況
・食事摂取状況、排泄状況、日中の活動
・理解力、意思疎通の可否
・入院前の生活、趣味、嗜好、家族状況
上記については、入院時にある程度得られる情報だと思いますが、患者さんの個別性にアプローチしていくためには、追加で以下の情報も聞けるといいですね。
・好き嫌いや食事内容
・食事時間、回数
・誰が作っていたのか
・誰と食べていたのか
・外食の頻度
・間食の有無
・食事でこだわっていた部分
これらの情報を統合することで、患者さんの人物像や大切にしていることが明確になり、関わり方指導内容により個別性を持たせることができます。
ただ、実際に業務をしていると、情報収集のための時間を確保するのは、なかなか難しいと感じますよね。
そこで、情報収集のコツをお伝えしておきます。
それは、わざわざその情報を聞くためだけに訪室するのではなく、患者さんとコミュニケーションをとる時間を情報収集の機会とすることです。
そのためには、得たい情報を前もって整理しておき、バイタルサイン測定や清潔保持、その他ケアの時間を使って、患者さんと積極的にコミュニケーションを図っていきましょう。
特に、食後の口腔ケアや内服介助の時間は、病院食の感想を聞いたり、患者さんの好みを知る絶好のチャンスといえます。
少しイメージが湧いてきましたか?
新人の間は、患者さんとのコミュニケーションがぎこちなくなったり、お話好きの患者さんで時間がかかってしまうということも多いと思います。
先輩看護師の関わり方なども参考にしながら、忙しい中でも効率的に情報収集する技術を身につけていけると良いですね!
アセスメント

情報収集ができたら、次はそれらをアセスメントしましょう。
アセスメントとは、患者さんの情報を整理・評価・分析することですが、わかりやすくいうと「患者さんを多角的にみて、どんなケアが必要か見極めること」です。
患者さんの病状や治療経過に合わせた指導はもちろんですが、より個別性を持たせるためには、患者さんからの会話で得た情報をもとに考えることがポイントです。
例えば、高血圧で塩分制限が必要な患者さんの場合を考えてみましょう。
客観的データ:
・高血圧で通院、内服治療中
・2日前に息切れを自覚して受診したところ心不全の兆候がみられたので入院となった
・血圧167/95mmHg 脈拍79回/分 SpO2 98%(酸素1L/分投与)
・降圧剤の追加、利尿剤投与開始
主観的データ:
・最近階段を登ったときに息が切れるようになった
・なんかだるいな〜と思うことが増えた
・通院のときに栄養士の食事指導も受けていたけどあまり意識していなかった
・昔からなんでも醤油をかけて食べる
・お酒はほぼ毎日飲んでいる
内服で血圧コントロールを図っている患者さんですが、うまくいかずに心不全を併発してしまいました。主観的データを見ると、退院に向けて生活習慣の指導が必要なのは明らかですよね。
「なんでも醤油をかける習慣がある」という情報を得たときに、疾患への影響を考えれば、醤油の使用を控えたり他の調味料で代用するなどが提案できそうです。
しかし、以前から栄養士の指導を受けているにも関わらず、食生活を改善することができていないのには、なにか行動に移せない理由があると考えなければなりません。
その方の生活背景を無視して一方的に伝えてしまうと、患者さんは心を閉ざしてしまう可能性があるので、しっかりアセスメントしたうえで関わっていく必要があります。
ここでポイントとなるのは、患者さんが醤油を使う背景について考えてみることです。もしかしたら、
・幼い頃からの習慣、実家の味付けが濃かった
・味が濃くないと物足りないという嗜好
・「醤油=安心」という感覚がある
・食卓に用意されているからついつい手に取ってしまう
・病気と食事の関係を理解していない、重要と捉えていない
・好きなものを我慢したくない
など、その人の「暮らし」や「価値観」が隠れているかもしれません。
治療と生活習慣にギャップが生じている場合は、そこを見逃さないことが重要です。
患者さんとのコミュニケーションを重ねて情報収集し、その都度アセスメントをするようにしましょう。
そうすることで、患者さん一人ひとりに寄り添った指導を考えることができます。
看護計画の立案

指導を行う際、もちろんいきなり患者さんの元へ行くわけではありません。今まで集めた情報をもとに看護計画を立案して、関わり方を整理する必要があります。
わかりやすいように、3−2「アセスメント」で例に出した「高血圧の患者さんに対する看護計画」を考えていきましょう。
看護問題:指導を受けても食生活を改善できない
看護目標:患者の病態に望ましい食事を理解し、言葉にできる
※看護目標は患者を主語とし、評価しやすく達成可能な目標を設定しましょう。
【O-P】
現病歴
既往歴
アレルギーの有無
バイタルサイン
随伴症状の有無
(意識レベル、頭痛・嘔気・嘔吐、立ちくらみ・めまい、発汗、四肢冷感など)
内服状況
血液検査(ALB、TP、WBC、CRP、Hb、電解質など)
画像検査(レントゲン、エコー)
心電図
ADL
リハビリ状況
食事摂取状況
排泄状況
日中の活動
理解力、認知機能
入院前の生活
趣味、嗜好
今までの食事指導に対する理解の程度
疾患に対する気持ち
家族状況
食事療法に対する家族の理解度
入院前の食生活
‐好き嫌いや食事内容
‐食事時間、回数
‐誰が作っていたのか
‐誰と食べていたのか
‐外食の頻度
‐間食の有無
‐食事でこだわっていた部分
【T-P】
患者の病態に合った食事を提供する
患者が食事と疾患の関係について具体的にイメージできるよう指導する
患者の不安な気持ちや食事への思いを傾聴する
患者の嗜好や生活習慣に寄り添って指導する
患者が主体的に考えることができるように関わる
生活の中で食事以外の楽しみがないか一緒に考えてみる
家族の協力が必要な場合は、家族に対しても指導を行う
【E-P】
高血圧と食事の関係について説明する(食事が高血圧を悪化させる仕組みなど)
現在の病態と食事の影響について説明する
(食事を改善した場合の未来と改善しなかった場合の未来をイメージしてもらう)
塩分の多い調味料(塩や醤油など)の代替案を説明する
‐出汁やポン酢、酸味、スパイス、薬味の活用など
満足感が得られる食事の取り方を説明する
‐食事に集中する、よく噛む、食感や風味を楽しむ、家族との会話の機会など
この看護計画はあくまで一例なので、患者さんの病態や状況に合わせて、追加・修正を行ってください。
他の疾患に対する食事指導の看護計画が知りたい方は、こちらに詳しく解説しているので参考にしてみてください!
看護計画の実施

計画を立案したら、次は患者さんに対して計画を実施していくフェーズへ入ります。
実施は細かく分けると以下の3ステップとなります。
- 事前準備
- 計画の実施
- 反応の観察・追加のアプローチ
実施の前後のステップもとても大切なので、ぜひ参考にしてくださいね。
事前準備
まず大切なのが事前準備です。
患者さんのもとへ行く前に、準備が整っているか十分確認しましょう。
例えば、必要な情報は把握できているか、指導に使うパンフレットに不備はないか、どういう流れで指導を進めるかなど、必要なことは事前に確認し、心配であれば先輩にもチェックしてもらうと安心ですね。
また、計画を実施するだけの時間が確保されているのかも重要です。
患者さんの1日のスケジュールを確認し、前もって「◯時から30分ほど、〇〇についてお話する時間をいただきます」などと患者さんに伝えておくと良いでしょう。
加えて、実施場所は患者さんのベッドサイド、またはカンファレンス室など、落ち着いて話ができる環境を用意しておくのが理想的ですね。
事前準備とは異なりますが、看護計画の内容をスタッフ間でしっかりと共有しておくということも大切なポイントです。
関わり方や指導内容を統一しておかなければ、患者さんが混乱してしまい、看護師に対して不信感を抱く原因となります。
必要であれば、カンファレンスを開くことも検討しましょう。
計画の実施
実施する内容は計画の通りになりますが、実際は患者さんの現在の理解度に応じて、段階的に指導していくことになります。
一度にすべての内容を指導することは、患者さんの負担にもなりますし、時間的にも厳しいです。
指導時間に関しても、患者さんが疲れない程度で設定し、体調に応じて臨機応変に変更しましょう。
反応の観察・追加のアプローチ
次に、患者さんの反応を観察して、必要であれば追加のアプローチをしていきます。
具体的には、こちらの指導や説明、声掛けに対して、患者さんがどのように反応したのか、患者さんが言ったことや取った行動、表情などを観察します。
ここでのポイントは、看護師が患者さんの気持ちをしっかり聞き出すということです。
例えば、「調味料は他にもこんなものがありますよ」という看護師の言葉に対して、患者さんが「う〜ん」と無言になったとします。この時、あなたはどういう心境になりますか?
「やっぱり味が濃いものがいいと思っているんだろうな」「指導にうんざりしているのかな」など、マイナスな反応と捉えて、指導を進めることに不安を感じる人もいるのではないでしょうか。
でも、これは看護師が受けた印象に過ぎません。
本当にそう感じているのかもしれないし、もしかしたら全く違うことを考えている可能性もあります。
患者さん自身、自分でも何が引っ掛かっているのかわからないという場合もあるので、
・「今の提案を聞いて、どのように感じましたか?」
・「少しハードルが高いですか?」
・「どういうところがそう感じますか?」
など、こちらが深堀りして聞いていくことで、気持ちが整理されることもあります。
食事指導では特に、患者さんの気持ちを正確に知ることが計画の評価にも影響するので、ここでは勇気を持ってしっかりと対話することを心がけましょう。
以上が看護計画の実施の具体的な内容になります。
評価・修正(例:SOAP記録)
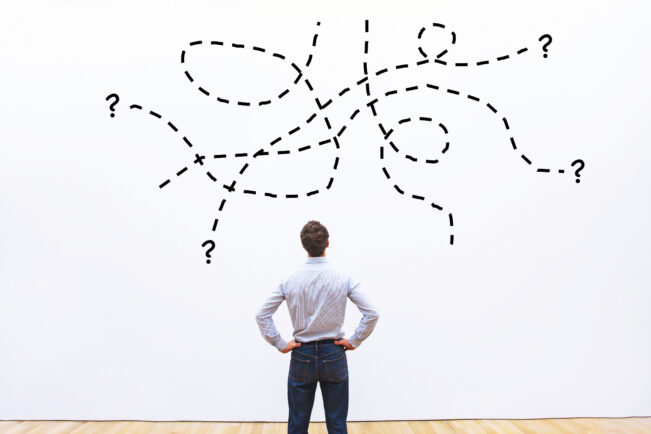
看護計画の評価・修正とは、実施した計画に対して患者さんの反応などから目標の達成状況を評価し、患者さんの状態に合わせて計画を修正していくことをいいます。
臨床の現場では、看護計画の評価日なども設定されて、定期的に計画を見直す機会を設けている場合も多いですが、本来は計画を実施する度に評価・修正を行うことが基本です。
ここでは評価・修正の方法をSOAP記録を用いて解説していきます。
SOAP記録のおさらい
評価・修正は、SOAP記録を用いて行いますが、まずは記録の正しい記入の仕方をお伝えします。
S:主観的データ
看護計画を実施する前後で、患者さんが発した言葉をありのまま記入しましょう。
患者さんが言ったことすべてを記録する必要はなく、あくまで該当する看護計画の評価に必要な情報のみ記入します。
O:客観的データ
看護師が観察したことや実際に行った計画の内容、計画を実施した後の患者さんの変化や反応を記入しましょう。
A:アセスメント
計画実施前後で患者さんに変化が見られたか、目標が達成されたかどうかを評価します。
目標が達成されなかった場合は、その要因はなにかを考えましょう。
P:プラン
計画の継続、修正、終了を評価して記入しましょう。
計画を修正する必要があれば、どのように修正するのかも具体的に記載します。
SOAP記録のポイント
SOAP記録の書き方をおさらいしましたが、評価をするにあたっていくつかポイントをお伝えしますね。
SデータとOデータは、あくまで該当する計画のO-Pに基づいた情報を記載するようにしましょう。
例えば、O-Pにバイタルサインの項目がないのに、バイタルサインを記入する必要はありません。
必要のない情報があると、記録が見にくくなり、評価の邪魔になってしまうので注意が必要です。
また、Oデータを記載するときにありがちなのが、アセスメントも含んだ表現になってしまうことです。
看護師の解釈や判断が混じらないよう、客観的で誰が見ても共通認識ができる表現を用いましょう。
次にアセスメントですが、アセスメントの最大の注意点は、看護師の主観で評価しないということです。
自分が患者さんに対して持っている印象や、普段の患者さんの傾向などが混じってしまうと、客観的な評価ではなくなってしまうので注意しましょう。
また、アセスメントはSデータ・Oデータに基づいて考察する必要があります。
もし、アセスメントをするにあたって不足している情報があれば、追加で情報収集しましょう。
プランでは、計画を継続するのか、修正するのか、終了するのかを明記しましょう。
修正する場合は、アセスメントで修正の必要性を明らかにし、具体的な内容をプランに記載します。
看護計画を修正・終了する際は、SOAP記録をした後に看護計画の修正や終了処理を忘れずに行いましょう。
基本的なことの説明になりましたが、以上が評価・修正の具体的な方法です。
食事指導では、患者さんへの説明や、それに対する患者さんの反応を記録していくことになります。
そのため、患者さんの表情や仕草などで看護師が主観的な解釈をしてしまいがちですが、3−4「看護計画の実施」でもお伝えしたように、コミュニケーションを駆使して、できるだけSデータとして情報を得られるように心がけましょう。
食事指導がうまくいく3つのポイント

ここでは、食事指導がうまくいくポイントを3つ紹介します。
- 患者さんの訴えを否定しない
- 患者さんの理解力に合わせて伝える
- パンフレットを活用する
看護計画を立てても、実際のコミュニケーションや関わり方に問題があると、指導も難航してしまいますよね。
患者さんの中には、指導されることに対して抵抗感を持つ人も少なからずいるので、指導を受け入れてもらえるように信頼関係を築きながら関わることが大切です。
コミュニケーションが苦手という方も、以下のポイントを意識することで、患者さんに寄り添った指導ができるようになります。
以下で詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
患者さんの訴えを否定しない
一番大切と言ってもいいポイントが、患者さんの訴えを否定しないということです。
患者さんが自分の気持ちを看護師に伝える時、どんな不安がありそうですか?
・言っても理解してもらえないんじゃないだろうか
・わがままな患者と思われるんじゃないだろうか
・「だらしない」「自分に甘い」「だから病気になるんだ」と思われていないだろうか
など、自分に対してマイナスなイメージを持たれることを不安に思う患者さんも多くいらっしゃいます。
そのため、本心を隠して当たり障りのない返答をされる方も少なくありません。
看護師は、このような患者さんの不安を先読みして、常に「私はあなたの気持ちを尊重しますよ」という態度で接する必要があります。
そうすることで、患者さんは看護師に心を開き、正直に自分の気持を話してくれるようになります。
具体的な会話例は、5.イメージしやすい!食事指導の会話例を参照してください。
患者さんの理解力に合わせて伝える
患者さんの理解力に合わせて伝えることもとても重要です。
その方の認知機能や性格によって、一度に理解できる量やスピードには個人差がありますよね。
それを無視して、「今日はこれとこれを伝えよう!」と一方的に指導してしまうと、看護師は達成感を感じられるかもしれませんが、結局患者さんには何も伝わらずに終わってしまいます。
そうならないように、事前に指導内容のボリュームや伝え方なども検討しましょう。
患者さんの理解度を確認する方法としては、指導した内容を患者さんに聞いてみるとわかりやすいです。
自分の言葉で整理しながらアウトプットすることで、患者さんの理解もより深まります。
ここで注意したいのは、患者さんにプレッシャーを与えないようにすること、うまく説明できなくても患者さんを責めるような態度にならないようにすることです。
例えば、「私が言ったことをもう一度説明してみてください」と言うと、「え?そんなの覚えてないよ〜!」と患者さんも困ってしまいますよね。
「塩分を控えることがなぜ大切なのでしょう?」「味が物足りないときはどうしますか?」など、細分化して質問をすることで、患者さんも答えやすくなります。
患者さんが理解できていないと思う部分は、もう一度丁寧に説明をして、理解度を確認していきましょう。
また、患者さんの特徴に合わせて、以下のような伝え方のポイントがあります。
・認知機能の低下や物忘れがある→患者さんの指導は簡単なものとし、家族への指導を重点的に行う
・几帳面な性格→病態生理やメカニズムを伝える、具体的な方法・時間・量などを指定する
・大雑把な性格→難しい内容にならないように注意する、本人のやり方に合わせた提案をする
・飽きっぽい性格→興味があることを明確にして指導に取り入れる、ご褒美を取り入れるなど習慣化する工夫を考える
このように、認知機能や性格によって、アプローチの方法も様々です。
患者さんの反応を観察しながら、関わり方を検討していきましょう。
パンフレットを活用する
指導をするにあたってかなり役立つアイテムがパンフレットです。
耳で聞くだけではイメージしにくいことも、パンフレットなどの視覚的情報があると、患者さんの理解もスムーズになります。
また、看護師にとっても、パンフレットを見ながら順序立てて説明することで、指導のハードルが一気に下がるので、ぜひ活用しましょう!
学生の時にパンフレットを作成した経験がある方もいるかも知れませんが、作るのに時間がかかって大変なイメージはありませんか?
実際の看護業務の中で、患者さん毎にパンフレットを作るのは現実的ではありませんよね。
もし相談できるのであれば、管理栄養士さんに使えるパンフレットがないか聞いてみるのも一つの手です。
既存のパンフレットはわかりやすく要点がまとめられ、デザイン性も考えられていて見やすいので、使わない手はありませんよね。
食事指導を頻繁に行う病棟であれば、指導用に「高血圧の仕組み」「高血圧と塩分の関係」「高血圧の食事ポイント」など、テーマごとに資料を作成しておくこともおすすめです。
ラミネートして指導の際に使用したり、必要時に原本をコピーして患者さんへ配布することもできます。
目標を記載しておけば、患者さんも意識して行動に移しやすいかもしれませんね。
こちらの記事では、パンフレット作成や指導に使える資料サイトを紹介しています。
よければ参考にしてみてくださいね!
資料作りは業務の負担に感じるかもしれませんが、チームで取り組めば負担は軽減されます。
なにより、看護師自身の理解が深まり、患者さんへの説明スキルも向上するので、一度取り組まれてみてはいかがでしょうか。
イメージしやすい!食事指導の会話例

実際の指導場面がイメージしやすいように、事例を用いて会話の流れをみていきましょう。
ここでは、「高血圧の患者さん」に対する食事指導の会話例を、3つの場面に分けて紹介します。
【患者プロフィールと経過】
Aさん 70歳 男性 妻、息子夫婦と4人暮らし
2年前に高血圧の診断を受け内服治療中であったが、2日前に息切れを自覚して受診したところ心不全の兆候がみられたので入院となった。
医師より高血圧食の指示があり、塩分制限がされている。Aさんは、食事時が薄味であることに対し、配膳するスタッフに度々不満を漏らしている。
通院中から管理栄養士の食事指導を受けていたが、自宅での食事は特に意識していなかった。
会話例① 病院食に不満がある患者さんとの対話
看護師:Aさん、病院のお食事はいかがですか?
Aさん:全然美味しく感じないよ。薄くて食べた気がしない。
お腹を膨らませるだけで、楽しみも何もないね。
看護師:そうですか、薄味で満足感がないんですね。それでは食事の楽しみがなくて辛いですよね。
お家ではいつもお醤油をかけられていたんですよね?
Aさん:そうそう、何にでもかけていたよ。
栄養士さんからポン酢に変えてって言われたけど、醤油とポン酢じゃ違うでしょ?
看護師:たしかに酸味がついているので、味は変わってしまいますね。わかります。
ポン酢の他にも代用できるものがあるんですよ。パンフレットで見てみましょうか。
Aさん:そうだね、どんなのがあるか教えてほしいな。
【解説】
看護師は、Aさんが治療食に不満を持っているという情報を得たので、食事に対するAさんの気持ちを聞いています。
不満を持った状態で指導を始めても、Aさんは指導内容を受け入れられないかもしれませんよね。
指導を行うにあたって、患者さんの不満感や不安な気持ちは、初めのうちに解消してあげましょう。
ポイントは、患者さんの訴えを否定せず、共感の態度で聴くことです。
「病気だから我慢は仕方ない」などという思い込みを持っていると、患者さんにも伝わってしまいます。
共感の姿勢とは、「Aさんにとっては辛いことなんだな」と患者さんの立場になって気持ちを想像し、それを相手に伝えることです。
そうすることで、患者さんは「この人は自分の気持に寄り添おうとしてくれてるな」「味方なんだな」と安心感を得ることができ、こちらの話にも耳を傾けてくれるようになります。
会話例② 患者さんの理解度を確認したいときの対話
看護師:ところで、Aさんは先生から今回の病状についてお話は聞かれましたか?
Aさん:聞いたよ。血圧の薬と、おしっこを出す薬で治療していくって。早く退院したいなあ。
看護師:早く退院して、美味しいご飯が食べたいですよね。
だた、今のAさんの病気は、食生活が大きく影響するので、そのままのお食事を続けていると、
更に悪化する可能性もあるんですよ。
Aさん:それも先生に言われたよ。薄味に慣れろってずっと言われてる。嫌になるなあ。
看護師:そうですよね、長年の食事を変えるのは簡単じゃないですよね。
病気と食事の関係については、しっかり理解できていると思いますか?
わからなかったら正直に言ってもらって大丈夫ですよ。
Aさん:味の濃いものが駄目ってことはわかってるけど、なんで駄目なのかはよくわからないなあ。
説明されたかもしれないけど、なんか難しくて。先生に何度も聞けないしさ。
看護師:そうだったんですね。
先生の話でわからないことがあるときは、後で看護師に聞いてもらっても大丈夫ですよ。
今日は、「塩分を摂りすぎるとどうなるのか」を簡単にわかりやすく説明させてもらいますね。
Aさん:はい、お願いします。
【解説】
ここでは、患者さんが病気や食事制限の必要性について、どのくらい理解できているのかを確認しています。
ここでは、「わかっていなくても大丈夫ですよ」というスタンスで患者さんに聞くことがポイントです。
理解しているふりをされると効果的な指導ができなくなるので、患者さんにプレッシャーを与えないように気をつけましょう。
医師から説明を受けていても、あまり理解できていなかったり、そこまで重要に捉えていないということはよくあります。
また、患者さんの中には、医師に気を使ってしまい聞きたいことが聞けないという人も多くいます。
医師の病状説明などの後には、わからなかったところはないか患者さんや家族に確認して、補足の説明をしたり、医師に追加で説明を依頼するなどのサポートも看護師の重要な役割ですね。
患者さんへ指導するテーマを伝えるときに、「病気と食事について」「食事制限の必要性」などざっくりしたものでは、難しい話をされるんじゃないかと身構えてしまう可能性があります。
少し噛み砕いて「塩分を摂りすぎるとどうなるのか」という具体性のある言い回しにすると、患者さんの抵抗感も少し和らげることができますよ。
会話例③ 指導後に患者さんの感想を聞きたいときの対話
看護師:食事を変えていくことに対して、気持ちの変化はありましたか?
Aさん:今までは、薄味にしろって言われるのが嫌で適当に聞いてました。
でも今日の話で、そうも言ってられないのかなって思いました。
看護師:自分でしっかり理解すると、向き合い方が変わってきますよね。
少しずつ、食事改善に前向きになっていただけると、私も嬉しいです。
Aさん:嫌だけど、頑張るしかないよね〜。
看護師:今日は疲れませんでしたか?
次回は、味付けなど具体的な方法についてお話できればと思っています。
Aさん:大丈夫でした。よろしくお願いします。
【解説】
指導の後は、そのまま終了するのではなく、患者さんに感想や気持ちの変化などを聞いてみましょう。
もし、食事改善に対してすぐに前向きになれなくても、患者さんの気持ちをそのまま受け止めてあげてください。
患者さんによっては、看護師の励ましで嬉しいと感じたり、モチベーションが上がる人もいるので、優しい声掛けをしてみるのもいいですね。
ただ、後ろ向きな人にそういった声かけをすると逆効果の場合もあるので、患者さんの反応を見ながら判断しましょう。
また、内容が難しくなかったか、時間は適切であったか、患者さんの疲労感はどの程度かなども聞いて、今回の指導を振り返る材料にします。
必要であれば計画を修正したり、次回の指導に向けての準備を行いましょう。
以上、3つの場面を紹介しましたが、少しイメージが湧きましたか?
もちろん、この通りにいかないことのほうが多いと思いますが、ポイントを抑えて関わることで、コミュニケーションをスムーズに図ることができます。
患者さんに寄り添った指導の会話例として、こちらの記事も参考になるので、ぜひご覧になってみてください!
まとめ
食事指導など、患者さんの生活に踏み込んでいかなくてはならない関わりは、看護師にとってもハードルが高いですよね。
いろんな患者さんがいるので、指導方法や関わり方に正解はありませんが、看護師として何を大切にするかを明確にしておくことはとても大切です。
患者さんに寄り添った関わりをすることで、信頼関係を築きながらスムーズな食事指導を目指しましょう!



コメント